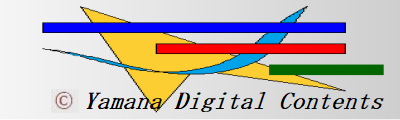封印の解けるとき Ⅰ
第一部 掘り出された想いの形見
注 これは、手元にある校正前の原稿を基にしているため、「奔馬」掲載文(ダウンロード対象)とはやや異なる部分があります。
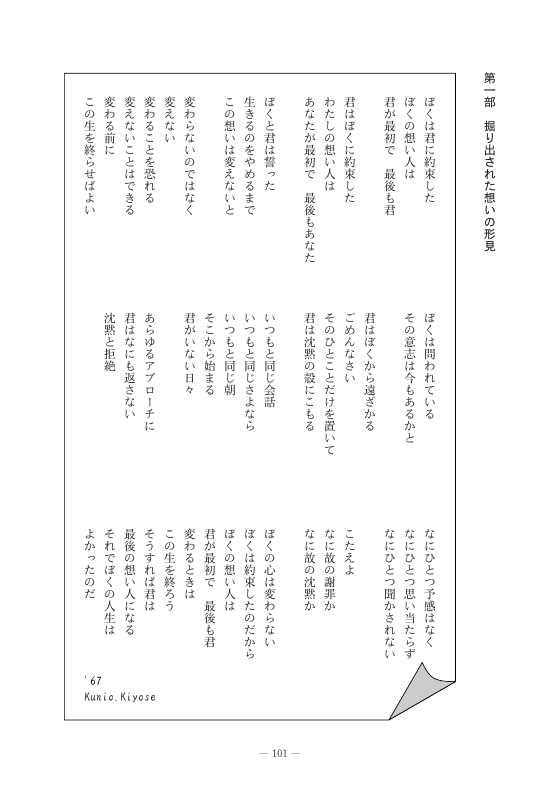
プロローグ
秘密を持つのは大人になった証
聖世邦夫はこのフレーズが好きだ。少女が、たわいのない隠し事なのに、その後ろめたさを言いわけしている様を惟わせる。
少女の秘め事はやがて思い出に変質する。秘密が思い出といわれるものと重なるのは自然である。異質なものであることもあるが、同じことが係わる人によって秘密になることもある。「秘密」は後ろめたく背徳の響きがあるのに、「思い出」といえば責める人はいない。
少女の秘密と違って大人の秘め事はおぞましい。そして、秘密を持たない大人などいない。生きていれば秘密は抱えてしまう。ただ、秘密と思い出の境界は曖昧である。大人の秘密は少女の隠し事に比べるべくもない。
秘密は翳がある。隠微である。しばしば淫靡としかいえないこともある。隠したくて秘密にするわけではなく、それを曲げてしか見ない人がいるから隠さねばならないこともある。干渉されるのが煩わしいから黙っていることもある。秘密は、それを許さない人によって創られることもある。そして、ひとたび隠したからには隠し続けるしかない。隠していたことがわかれば責められるが故に、隠したことが悪になるが故に、封印をして隠し続けるしかない。どこまでも、どこまでも。しかし、封はいつしか剥がれることがある。
思い出も秘密も形になって存在する。
人は目に見えない記憶には確かな存在を覚えない。曖昧で、不確かで、見ることも触れることも叶わないが故に目に見える形で残そうとする。日記に記し、手紙を残し、一瞬の事実を写真に残そうとする。それが秘密になる日がくるかもしれないのに。心の中は覗かれないが、見えるものは消さない限り隠しても現われる恐れがある。暴かれなくても露見してしまうことがある。消さなかったことを後悔する日が来ないとは限らない。
形あるものは廃棄できる。燃えるものは焼き尽くすことができる。しかし、秘密は一人で持つとは限らない。共有する相手があることはリスクを持つことになる。自分さえ洩らさなければ、人の目に曝すようなことをしなければ、思い出は美しく、甘味であるまま朽ちて消滅する。秘密は、だれをも傷つけることなく消える。だからこそ、閉じ込めている秘密を洩らすことはだれも望まない。人はだれも墓場まで持っていくつもりでいる。「秘密」は秘密のまま、「思い出」は思い出のまま、自分の肉体の消滅とともに消滅すると信じている。その時までは心の封印を解くまい。だれも知らない、だれも触れることができない、だからだれにも剥がされる恐れはない。
だが、聖世邦夫はこのごろ思うのである。その封はそれほど信頼できないではないかと。自分自身が己の秘密を洩らしてしまわないかと不安になる。なんと恐ろしいことではないか。暴露されるのではなく、自ら秘密を曝け出す恐怖である。秘密を封じ込めておくには強靭な意思と精神力が要ることを老いて初めて思い知る。若いときは意識することもなかったが、体力と気力の衰えはその意思力と精神力を無慈悲に削ぎとっていく。昔の記憶のみ残して。それを際限なく、見境なく、垂れ流す老人もいる。認知症などと言い換えても所詮はボケである。勇ましい武勇伝なら罪はない。傲慢な自慢話は嫌われるだけで終る。しかし、秘めておかねばならない秘密を相手かまわずボロボロと吐き出しているとしたら・・・。
聖世はその姿を自分に置き換えては戦慄する。今すぐにでも自分の生を終わりにしてしまいたい衝動にかられてしまう。その前に、あの秘密、この秘め事をすべて始末しなければならない。たとえ黴が生えているほど古い秘密、当人にとっては歴史でしかないにしても、無害というわけにはいかない。事実であっても真実であっても、秘めたままにしておかねばならないことは、歴史にも、偉人にも、そして聖世のような小市民にもある。自分が自分をコントロールできるうちに、日記も古い手紙も写真も、遺されたものはすべて消し去ってしまいたい。それができるなら。