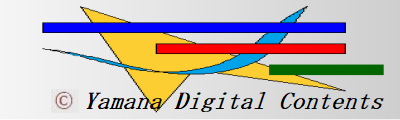一 封印された思い出
充分に大人であった。秘密をたっぷりと封じ込めている大人であった。それが、現在の聖世邦夫である。
聖世は、読み込んでいた本から目をあげて書棚の写真盾に目をやった。写真そのものではなくて写真を貼付した学生証が入れられている。学生服姿の写真には大学の刻印があるはずである。ただ、そこから見るには小さ過ぎた。本を閉じて立ち上がると、本棚の前に立って学生証の中の小さな自分を見詰めた。
『細かったな…』
実際、写真の聖世は、詰襟の首は細くて頼り気なく弱々しかった。それでも、その頃の憂鬱と翳は学生服の鎧でかろうじて隠されていた。かつて、医者から「命にかかわる」とまでいわれたほど痩せていた頃の写真を見つめながら、聖世はため息をついた。あの頃の写真はこの小さな額に入れたものしか残ってないのだろうか。もちろん、写真などなくても、その気になれば、この頃の写真はたいてい思い出せる。隣に写っている少女の顔と共に。しかし、どんなに鮮明な記憶であっても、イメージを絵にすることは難しい。記憶として認識する「写真」は単なるイメージでしかない。頭の中に浮かんでも眼に見えるものにはとうてい敵わない。記憶に残せば写真は要らないというのは、その意味では嘘である。
今日に限って、その写真のことが気になった。彼の少女のことは思い出しても、写真のことを思い出すことはこれまでなかったのに。
「捨てた筈がないとすれば、どこにあるのか…」
聖世は戻らない日を思い出していた。命の高揚に満ちていなければならない時代なのに、喉元に逆流する胃液のように苦酸っぱい味のする絶望を抱えていた時代。
聖世は記憶の中の「絶望の味」を飲み込んだ。甘味な思い出は甦らず、忘れていた言葉の断片が塊になって頭の中を浮遊した。塊を解いてはならない。そんな無益なことをする意味などない。それがわかっているのに、今日に限ってボロボロと塊が解けていく。頭の表面に断片的な言葉の切れぎれとして張り付く。確かにそれは紙に書かれた言葉。想いは紙に化体している。抑え切れない、振り切れないのなら、逆に覚悟を決めて言葉の断片を繋ごうとするが、意味ある文章にはならない。
食べること、歩くこと、人に会うこと、目覚めていること
憂鬱だ
終れば憂鬱な明日はもう来ない
苦悩の後に何があるというのか
この想いが、歴史になり、化石になるまで
いまひとたび 哀れいまひとたび
思い出せるのは途切れ途切れの断片でしかない。もどかしさに、聖世は不完全な忘却を呪った。
あれは何に書いたものだったろうか。大学ノートに綴った日記だったろうか。便箋に書きなぐったのだろうか。いや、そんなことはどうでもよい。問題は、世界のどこかにそれが存在していることである。聖世は確かにそれをある所に埋めて封印した。それでこの世には存在しないことになると信じて。
何故それを埋めに行ったのか、その当時の自分を、もう定かには思い出せないのだが、生き続ける気はなかったような気がする。具体的に自死を決意していたというわけではないが、漠然と自分の生を断つつもりでいたような気がする。その後に遺したくないと思うからこそ、あれを埋めに行ったのではなかったか。それなら、現在は自分にとって「思い出」になるが、或る女との関係では「聖世の秘密」でもある。万一、発見されるようなことがあれば、彼女を特定するのにさほど障害はない。なにもかもそのままにして埋めたのだから。
始末をつけておかねばならない理由を見つけられたことに聖世は満足した。埋めるときは見つけられることなどもとより想像していなかった。焼いてしまえば終ったものを、わざわざ遠くに埋めに行くとは・・・。本当は、想いの残骸までも消滅させてしまうことに躊躇したのであろう。掘り出すために再登山することを予想していたのではないか。もう、その予想の限界線を遥に超えているが、今こそ、思い出となった過去を、想いの残骸をもう一度見ておくのも悪くはない。それを始末するにはそれなりの体力と精神力が要る。時間はあまりない。聖世は、もう一度彼の地に行くことを決めた。
二 埋葬の日
出発は10月22日の夜行列車であった。何年のことかは正確に思い出せなくても、月と日は間違いない。前日は 10・21「ジュッテンニイイチ」国際反戦DAYということで、聖世はデモ隊の最後の総括場所となっていた市役所前で「反戦会議」派の学生部隊に混じって座り込んでいた。市役所前の広場は、セクトの旗と、いわゆるラジカル系の学生・労働者の隊で埋め尽くされていた。盛り上がらなかった日韓条約粉砕闘争・原潜寄港阻止闘争のことを思うと、久しぶりの「大動員」で集会参加者は熱かった。広い御池通りに溢れて座り込んでいる最後尾の学生らは車の通行を半ば遮断していた。反対側には機動隊が六列の重厚な隊列でデモ隊を威圧していた。ジュラルミンの盾が車のヘッドライトに反射して時折鈍く光る。座り込んでいるデモ隊の一番前の方では、次々とセクトの幹部が勝利のアジテーションを繰り返していた。指揮車のライトがアジテイターを照射する度に、ヘルメットに手拭で覆面した汚れた男の顔だけがスポットライトを当てたように浮かび上がる。もう少し清潔な手拭いで覆面すればライトアップの効果もあるのに、なぜ好んでうす汚れた手拭いを顔に巻くのか。聖世がこの日のデモに参加したのは、セクトに属していたからでも、彼らの主張に賛同したからでもなかった。ベトナムで、カンボジアで、ラオスで、アメリカとソ連・中国が戦争をしていた。そこではまぎれもない虐殺が行われているのに、地雷を踏む恐怖も、銃剣を突きつけられる不安もない日本で、何もしないで、女に見放されたことでウジウジしている自分が許せなかった。何もしないことは、虐殺に加担していることになるといわれると、そんな気もしないではなかった。この日にデモに参加したことで、できたら、学生としての義務を果たした気分になりたかったが、そんな安易なことがあるはずがなかった。
セクトのリーダーが他のセクトを意識して強がりをさらにエスカレートして声高に叫ぶ。これまで見たこともない大勢の聴衆を前にして、舞い上がり、昂ぶって、嬉々としてアジっているうちに時間は過ぎていった。
我々のー、世界の人民と連帯したー、沸騰するー、怒りの声とー、我々のー、圧倒的に優勢な隊列を前にしてー、あのー、日帝と政府権力はー、恐怖してー、我がー、革命同志の隊列にー、武装機動隊のー、狂暴なー、弾圧を試みてー、我らの前進をー、阻もうとしたがー、圧倒的なー、大衆の怒りとー、我が戦闘部隊のー、激烈な反撃の前にー、遂にー、その弾圧を諦めざるをえなかったこととー、そのー、熱いー、学生と労働者のー、連帯がー、本日のー、このー、市役所前広場のー、完全制圧とゆー、大勝利をー、勝ち取ったことをー、報告するー、・・・・
聖世は猛烈に腹が空いてきた。とっくに夕食の時間帯は過ぎている。「もう、これでいいや」と聖世は隊列から離れることを考えていた。そうしたところで、「闘争の放棄」というのは、聖世には当てはまらなかった。それでも座り込みで「連帯している」仲間から抜け出すのは後ろめたかった。しかし、いずれのセクトによる「勝利」でもないのに、自己誇示ばかりの大袈裟な勝利報告にノンセクトの学生らが飽きかけて、野次を飛ばし始めていた。自分にはここらが潮時だと聖世はその場を抜け出すことを考えている。ここ数日は、散った恋と傷だらけの想いの整理に追われていた。どう生きていけばよいのか、生き続けることが出来るのかさえわからない日々に、ともかく決別するために彼女にまつわるものは捨てようと決めた。そのための整理と旅仕度をすることが、とりあえず聖世を生きさせているようなものであった。旅の仕度を終えて、出発を翌日に控えた今日、このデモに参加して久しぶりに何かを期待する心境になっていた。まったく根拠がないのだが、翌日からの一人旅で腐った自分にケジメをつけられそうな期待感がかすかに湧く気がした。
不意に、座り込んでいるデモ隊の最後部で怒号と悲鳴があがった。機動隊が排除の実力行使に出たのである。デモ隊は大混乱になった。前の方では、指揮者がスクラムを組めと叫んでいるが、聖世は逃げ場を探した。スクラムで対抗できると本気で思っているのか。抵抗すれば公務執行妨害で容赦なく拘束されることはだれでも知っている。機動隊の解散命令を無視し続けたデモの指揮者こそ無責任なのである。自分の人生を棒にふるかもしれないのに、ここで機動隊に抵抗しなければならないほど自分に関わる問題などあろうか。悲壮感も信条もない。熱気に身を任せるほど愚かでもない。それだからこそ、この夜の聖世は明日を生きようとしていた。
ぶつかり合い、揉みくちゃになりながら聖世は人間の塊から必死で抜け出した。捕まりたくなかった。捕まれば翌日からの旅に出られなくなる。その思いが聖世を走らせた。河原町通りは逃げる腰抜け学生がバラバラになって走っていた。聖世もその腰抜け集団の中にいた。重装備の機動隊に本気で追いかける意思はないはずだが、不意に横道から別働隊が襲ってくるような恐怖があった。大学の正門を越えたとき、ぜいぜいと息を切らせながら聖世はやっと安堵した。明日は出発できる。
その日は、この山の裾にあるユースホステルから登山に出発した。湖のすぐ傍にあるロッジ仕様のホステルであった。
前日、夕暮れ時に、聖世一人が乗っているだけのバスがここに着いたとき、バスから降りた聖世の目に見えたものは、大悲山であろう薄い影と湖に張り出して造られている休憩所の傘屋根くらいであった。ヒタヒタと水の音がするので自分が湖のほとりにいるのはわかるが、霧が白く水面を蓋っていて湖面がまったく見えなかった。地面を這う霧も濃く、道路と湖岸の境さえ見分けがつかず、聖世は歩くのに恐怖を覚えた。しかし、もう引返すバスは行ってしまった。予約してあるホステルに行くしかないし、それを探さねばならない。
ホステルは湖に沿った広い道路を行けば横道にそれなくても在ることが地図でわかっていたので、かろうじて足元だけは見える舗装された道に沿って歩いた。人影が見えないのではなく、本当に人の気配がまったくなかった。聖世はこんなにも何もない所に驚いていた。夏場なら多少の観光客もいるのだろうが、紅葉の季節も終ったこの時期に、こんなところに来る人間はいない。いうなれば、何も見るべきものがないところであった。ホステルがあること自体が不思議なくらいであるが、こんなところでも、いや、こんなところだからこそ学生らの合宿に使われることがあるとを後から聞いて聖世は納得したものである。
そのホステルは、だだっ広い原っぱのようなところにポツンと建っていた。それで見分けがついたが、ほんのわずかの距離しか歩いてないのに聖世はひどく疲れた。こわごわ歩いてきたので時間もかなり経っていた。すぐ傍まで寄って、それが目指していたホステルだと確認できたとき、聖世はとりあえず安堵した。
洒落た湖畔のロッジという体のホステルの玄関戸には鍵がかかってなかった。中に入ったが誰もいないし、だれも出迎えてくれない。大きな声で奥に向けて挨拶すると、やっと痩せた中年の男が出てきて「聖世君だね」とめんどくさそうにいった。一瞥しただけで後は目も合わそうとしない。他にだれもいる様子はなく、ここのマネージャーらしいが、ぶっきらぼうで無愛想な男であった。建物の中は天井が吹き抜けで高いのだが、暖房もいれてないので寒々としていた。案内された部屋は山小屋のように二段棚のベッドになっていた。両サイドにあるが、その片側の下の棚にだけ毛布が置いてあって、男はそこを使うように指示した。ザックを置いて、聖世が改めて「お世話になります」と挨拶しても、男は食事は下のリビングに用意してあるからいつでも食べられること、風呂は女風呂の方を沸かしてあるからそちらに入るようにと、無愛想な対応はまったく変わらず、いうだけのことを言っただけで部屋を出て行った。
小さな風呂に入って汗を流したあと、着替えて「食堂」と書かれた部屋に行ってみたが、電気も灯いてないし、テーブル上に椅子がひっくり返して置かれている有様であった。反対側の「管理室」と白いプレートの貼ってある部屋に灯りが灯いているので行くと、四人がけのテーブルに学食で食べるような何の変哲もない「洋食ランチ」が置かれていた。スープも味噌汁もなく、ハンバーグは冷めているし、米飯ではなく不味そうなパンが二個ランチ皿に盛られていた。男の姿が見えないので、聖世は大きな声で「いただきまーす」といって食べ始めた。時間は未だ五時半であり、お腹も空いていないので、冷めて不味い「洋食ランチ」を残らず食べるのが苦痛であった。せめて熱い珈琲はないかと見回したが、望みようもなかった。水以外にお茶さえ飲めない食事を済まして、流しに食器を洗いにいくと、男がすぐ隣の居間らしい部屋で雑誌を読んでいるのが見えた。たった一人の客の話し相手すらする気がないらしい。
心細い思いをしてようやくたどり着いた宿である。話し相手がほしいとは思うが、この男と話しても楽しくなることはあるまいと諦めた。せめて食事くらい温かいものが食べたかったのに、土産物屋か食堂の残り物のような不味いハンバーグを食って、食器の洗い場で水を飲む惨めさに聖世は早々にベッドに戻って明日の予定を練ることだけを考えることにした。ただ、明日に登る大悲山の情報は得ておかねばならない。聖世は存在と名前しか知らないのだから、山の情報はこの男から聞くしかなかった。
「ごちそうさまでした」
聖世はソファにかけて雑誌を見ている男に声をかけた。男は目を上げて、流しの様子を一瞥してから「ごくろうさん」と言葉だけの返事を返した。「お風呂は、女湯の方を沸かしてあるから、間違わないように」というと、もう話すことはないというようにテレビのスイッチをいれに立ち上がった。聖世は、慌てて話しかけた。
「あ、お風呂は先に入りました。ありがとうございました」
男は、聖世が風呂上りでセーターに着替えていることも気付いてない。どうでもいいというふうに
「そうか。それならいいよ」
とだけいう。
「大悲山というのは、登山道はいくつもあるのでしょうか。登るのにどのくらいみておかねばならないか教えていただきたいのですが」
男は、テレビのスイッチをいれようとしていた手を止めて聖世の方を振り向いた。不思議そうな顔をしているが、何もいわないまま聖世を見ている。聖世は、訊いたことを後悔していた。そうだ、この男に何か訊くなんて、なんて馬鹿なことを自分はしているのか。
「あ、いいです。明日、霧が晴れたら見えるはずですし、地図もありますから、自分で調べます」
と、申し訳なさそうに聖世がいうと、男はやっと応えた。
「登山道は、ホステルの前の道を少し行くと、山の方へ逸れる細い道があるから、それを山に向かって行けば一本道で行けるさ。他にも地元の人が登る道はあるけれど、今言った道からの登山なら迷わないで済むと思う。登山と言っても坂道はたいしたことはないから4時間もみておけばいいだろう」
思いがけなく教えてもらって、虚を突かれた聖世の方が返事すらすぐにできないでいた。そんな聖世を見て、眉間に皺を浮かばせた男はぶっきらぼうに訊いた
「この時期にあんな山に登っても何もないのに、どうしてわざわざ登ったりするのかね。あの山を登山の対象すること自体がおかしいけど。だいたい、こんな時期にこのホステルに泊まるホステラーだっていないのに。本当はこんなロッジじゃなくて、もっと客の呼べるホテルにするべきなんだ・・・。この時期は閉めていてもいいくらなんだが、連盟の方が雪の積もる一二月までは開けておけというので開けているだけなんだ。まったくバカらしい・・・」
迷惑だといわれているようなものである。しかし、だからといって、営業している以上は、ホステルのマネージャーとしてその態度はなかろう。いっつも、ホステラーには説教臭いことばかりいって、寝具のたたみ方から食器の洗い具合、言葉づかいまで小うるさいことをいうくせに。それでも、ホステラーは反抗できないことになっている。
「ご迷惑をおかけします。『大悲山』という名前に惹かれたのと、あまり登る人もいないらしいと聞いたもので、行ってみたくなったのです」
聖世の正直な答えである。
「死に場所としてはダサいよ」
!そうか、この男はそんな風に自分を見ているのか、と聖世は納得した。しかし、それならもう少し話の仕方もあるだろう。自殺するのではないかと疑うホステラーになら、思いとどまらせるくらいの優しさなり厳しさがあってもいいだろう。もっとも、聖世がそんな対応を期待しているわけでは毛頭なかったが。実際のところ、自殺を決めてここに来た者なら、それくらい突き放されて厄介者扱いをされた方がいいのかも知れない。ダサいといわれたからといって、場所を変える必要がどこにある。当人がここまで来て、実際にそこに立ってみて、最後の決断として決めたのならそれでよいではないか。
聖世は議論する気などなかった。死ぬつもりではないが、似たような心境ともいえるのだから。しかし、そんなことをこの男に話してなんになろう。
「死に場所にしようなんて思ってません」
「そうかい。ま、いいけど、名前のせいかどうか知らんが、結構あそこで死ぬ奴もいるのでね。こんな時期だと気付かれないまま腐ってしまうかもしれん。それでいて、春になったらいやでも見つかる。迷惑なことだ」
男は、それだけいうと、結局テレビのスイッチはいれないで、雑誌を閉じてテーブルに放り投げた。
「今夜は君だけだから、ミーティングも何もないから部屋で好きにすればいいよ。俺は少し出かけるが、ドアの施錠はしていくから」
この霧の中を、どこに行くのかと聖世は訝しんだが、もう、この男のことを考えるのは嫌になっていた。出かけてくれるなら、この館に一人になるが、その方がずっと気楽だと思った。どうせ、明日の朝食も期待できない。手持ちのインスタント珈琲でパンでもかじるしかないだろう。
「おやすみなさい」
と聖世はいい残して寝台棚のある部屋に向かった。
灯りをつけたが、照明がにぶくて部屋中は薄暗かった。聖世はザックから「その箱」を取り出した。最後の見納めをしておこうと思ったのである。自殺した人の遺骸さえ腐るまで見つからないような場所なら、上手に埋めればだれかに発見されるような心配もないということになる。
木箱を選んだのは朽ち果てることを望んだからである。たいして大きくもない手文庫程度の木箱だが、ザックの中ではかさばった。こうして取り出すと、ザックに十分のスペースができて、水筒、アノラック、着替えなどの必需品が形良く納まることになった。それだけ、その木箱は余分な荷物だったのである。いよいよ、これを捨てるときがきたわけだが、そのときは、このザックのように、自分の心も気持ちも軽くなってスッキリするのだろうか。聖世は何度もその時のことをイメージしようとしたのだが、この今になってもイメージできないでいた。「明日になれば嫌でもわかる」と自嘲するしかなかった。
聖世は木箱の上蓋を取った。封筒に入ったままの手紙の束と大学ノート、数枚の写真、それで総てであった。このなかにどれだけ想いが込められているか。それなのに、なんという軽さなのだ、これは。想いなんて、しょせんそんなものか。聖世はノートも手紙も開けなかった。読み返す必要などない。なにもかも、どれもこれも、見なくとも目の前に思い浮かべることができる。彼女の手紙は暗記してしまうほど読んいた。それだからこそ、突然の決別宣言は不可解であった。手がかりは何一つ見つけられないまま、不可解は謎になり疑いとなって凝固してしまった。
聖世は手紙の束に触れただけで決別の儀式を終った。写真だけは手にとって見詰めた。見詰めていたらジワジワっと輪郭が崩れた。喪ったその時を思い出した泪のせいで。聖世は写真を箱に戻して蓋を閉じた。ザックにしまうと、もうすることがない。ベッドの上で胡坐をかいて、長い夜をどうして過ごそうかと思案したが、何も思いつかないので、ザックからポケットウイスキーの瓶を取り出して飲んだ。禁止されているが、だれもいないのだから問題にならない。ザックのポケットから萩原朔太郎の詩集文庫を取り出して頁をめくった。「大渡橋」が目にとまった。
いかなれば今日の烈しき痛恨の怒りを語らん
いまわがまづしき書物を破り
過ぎゆく利根川の水にいつさいのものを捨てんとす。
われは狼のごとく飢ゑたり
しきりに欄干にすがりて齒を噛めども
せんかたなしや 涙のごときもの溢れ出で
頬につたひ流れてやまず
朔太郎も強がっているだけの負け犬のような気がしてきた。利根川に流すのと自分のように山に埋めるのと、どちらも似たようなものだと思う。
そういえば、この箱の中の最後の手紙にも詩を引用していたはずである。未練男が恰好つけのために使う手なんだろうが、考えてみればすこぶる格好悪い。自分の言葉で振り向かせられないからといって、著名人や詩人の言葉で何とかしようとすることこそ情けない。しかし、今なお鮮明に憶えているのは、それが自分の想いにぴったりだったからだろう。あれは北原白秋だったろうか。
やわらかきかかる日の光のなかに、
いまひとたび、あわれ、いまひとたび、
ほのかにももらしたまいね、
われを恋うと。 「断章二十五」
あたりまえのように聞いていた「あなたが好き」を聞かなくなってどのくらいになるだろうか。聞けなくなってから思う、その言葉の愛しさ。聞けないことの寂しさ。「われを恋う」か…素敵な表現だ。逢うことも、話をすることも、手紙をもらうこともなくなった自分に再びもらされることはないだろう。
明日が過ぎれば、この旅の目的は終る。大渡橋に行ってみようか。聖世はぼんやり思ってみたが、酔いがまわってきた。眠っている間だけが忘れていられる時間である。無理に目覚めている理由などない。聖世はベッドに這い上がって、そのまま眠りに落ちた。
三 想いの形見捜し
四月の下旬ごろは、少し雨模様だと中部地方の山々は中腹辺りから霧に隠されることがある。山間部では春にもかかわらず湿った空気が冷たい。高い山の頂上付近には、まばらな桜の木がだれにも愛でられないまま花を残していた。樹木の葉が青葉の鮮やかさを備えるにはまだ時間が要る。山は春の向こうの夏の到来を待っている状態であった。
朝の食事前に入った露天風呂から見た大悲山は、碧い空を背景にして明るい陽光にくっきりと見ることができた。さして高くもなく、美しくもなく、むしろこんもりとそこだけ盛り上がった不恰好な山である。どうみても露天風呂からの景色にふさわしい山ではないし、湯に浸かっている誰もが興味を向けることはなかった。ただ、見上げる空は、白い雲がところどころあるものの、春らしい明るい透明なブルーであった。露天風呂の入浴者は、気持ちよく晴れた空を見上げて満足そうであったが、だれも大悲山に関心はなさそうであった。
しかし、今、聖世邦夫が息を切らしながら登りつつある大悲山の山道はじっとりと湿っている。霧が山道をモソモソと這っている。登るにつれて霧は濃くなり、聖世の着ているアノラックがじっとりと濡れてくる。額も頬も冷たい水の膜が貼りついたようで気持ち悪かった。両側を山の斜面に挟まれた谷あいの細い道は、険しくはないが勾配が段々と増しているのは確かである。狭い視界からのぞめる空は、朝の空と違ってどんよりと暗い雲で蔽われていた。あとどれくらい昇れば頂上なのか、聖世には皆目わからない。あの日は、どれくらいかけて登りきったのだろう。
聖世がこの山を登るのは初めてではなかった。一度だけだが、ずっと昔に登ったことがある。あの時、聖世は若かった。22歳の頃の脚力で登った経験など、仮に憶えていても、それで今回の登山に要する時間を計ろうというのは意味がない。そんな当たり前のことに気付いて聖世は落ち込むしかなかった。そう、何もかもあの時とは違うのである。だが、あの時の落し物は始末しておかねばならない。この旅の目的はそこにあったが、同時に、懐かしい当時の自分を振り返ることも期待している。聖世は、あがってしまった息を整えながら、今の体力にあわせてゆっくりと坂道を登った。
誰にも会わない登山道であった。頂上に何があるわけでも、特に眺望がいいわけでもない山なのだから、好き好んで登る登山者などいないのであろう。あの時も、だれにも会わなかったことを聖世は記憶している。だからこそ、ここに決めたのだから。
聖世が頂上の狭い平地にたどり着いたのは昼を過ぎるころであった。途中でだれにもすれ違わず、この頂上にも人の姿はない。本当に人の寄りつかない山である。あの日もそうであった。そんなに高い山ではない。夏なら、子供が軽装で登って降りるだけの遊び登山でもできるほどである。ただ、地元に子供がいるとも思えないし、いたとしても虫捕りにくるくらいで、薄暗くて湿気た雰囲気は好かれないだろうと思われた。頂上といっても、標識など勿論ないし、展望台もベンチもない。ただ、低い薮がある他は湿気を含んだ黒い地肌の地面に雑草が生えているわずかばかりの平地があるだけである。荒地と表現するのも気が引けるほど貧弱なこんな所に…と聖世はここを選んだあのときの自分を信じられないでいた。その時の心境を思い出そうとするのだが、断片的な記憶しか浮かんでこず、そこから当時の心を推し量るのは難しかった。
しかし、やはりその場所に立つことで甦ってくる感慨も確かにある。この山に到るまでの旅のことを、この山を下りてからのことを、聖世は思い出していた。封印していたものを掘り出すためにここに来たのだ。薄れかけた思い出も今日だけは途中で仕舞い込むことはするまい。
ぼんやりとその時のことを思っていたら、湿気をたっぷりと含んだ霧のせいで汗をかいていた躰が冷えてしまった。聖世は寒気に身震いした。現実に戻って辺りを見廻すと、さすがに頂上は風があるため霧が流されているぶん視界は登山道とは比べものにならないほどよかった。辺りの樹木、地面の雑草も、多少は白く靄っていたが、しっかりと見て取れた。
聖世はその場所を探した。四〇年も前の記憶が頼りになるはずもないが、ここの形状が特に変わったようには思えない。聖世は懸命にその時のことを思い出そうとしていた。目印になるようなものはなかったが、登山道が頂上の平地につながって途切れる辺りではなかったか。しかし、道がどこで途切れているのかさえ雑草に覆われて見分けがつかない。
それと思われる辺りは草が茫々と生えている。それでも、概ねの範囲は特定できた。聖世はザックから折りたたみのピックとスコップを取り出して草むらに尖ったピックを打ち込んだ。湿気を含んだ土にめり込んだ先を刳ってさらに次を打ち込む。柔らかい土は簡単に掘り返せた。かなりの範囲を掘り返して根こそぎ抜いた野草はその都度放り投げていった。目指すものは土下数センチくらいにあるはずである。それを埋めたときは小さなスコップで掘ったのだから、いくら柔らかい土だったとはいえ、深くは掘れなかったと記憶している。風が渡るだけに頂上は寒いのだが、聖世の額から再び汗が噴き出していた。もはや見つけるまで辞めるわけにはいかない。聖世はひたすらピックを打ち下ろし、掘り返すことを続けた。
春のことである。雲の裏にぼんやりと在る太陽が沈むにはまだまだ時間があった。それなのに冷気が地面を這うように広がる。その冷気が、あれほど噴き出していた額や首筋の汗が乾いて肌を冷やしていくにもかかわらず、聖世は呆然と立ち尽くしていた。冷気に冷やされてアノラックの下の躰も徐々に汗が冷めていた。宝探しのような気分もないではなかった。期待していなかったといえば嘘になる。見つけられると期待し、信じたからこそこんなに一所懸命に掘り返したのだ。その熱に冷水をかけられた。冷気に躰が冷えるよりも、この精神に浴びせられた冷水に聖世は何も考えられないで、その場に立ち尽くすしかなかった。
捜し物は見つかった。湿った土にまみれてその箱は出てきた。四〇年近くを経て、なおその時のままの木箱を掘り当てた瞬間、聖世は安堵と幸運の心地よい幸福感に浸っていた。その箱を開けるまでは。
聖世は、当初はその場で箱を開けずにいったん持って山を下りようかと思った。土を落として、手も洗って、清めてから中のものをゆっくりと改めるのが相応しい。なんといっても四〇年ぶりである。しかし、箱に鍵がかけられているわけではないし、とりあえずは中を確かめたいという自然な誘惑に蓋をつい開けてみた。中に何を入れていたか正確に憶えているわけではないけれど、その様子は明らかに記憶とは違った。というよりも、中身がまったく別物なのである。入れてあったはずのものが何もなくて、代わりに分厚い便箋のようなものが透明な袋に厳重に梱包されて入っていた。聖世の秘密はだれかに見られていたことが歴然としている。しかも、そのすべてを持ち去られてたのである。聖世の頭はマッシロになっていた。
聖世は箱の中の便箋を取り出した。それはビニール袋に入れてあったらしいが、袋自体は劣化してボロボロになっていた。しかし、ラップで梱包されていたことで便箋自体にはさほどダメージがない様子であった。二つ折りの便箋を開くと、あきらかに万年筆で書かれたとわかる濃い青色の文字が並んでいた。紙は変色していて、文字も湿気で少しだけ滲んでいたが読むのになんの支障もなかった。聖世は、一瞬自分が埋めた箱ではないことを願ったが、泥土を落とさなくても、その手紙は、まぎれもなく聖世の埋めた箱であると指摘していた。そして箱の中身は、その手紙の書き主が「預っている」という。そのことだけで、大恥をかいていたことを悟った。知らない間ではあるが、だからこれまで平気でいられただけである。知ってしまった今からどうすればいいのか。聖世は、思考が停止したまま何も考えられなかった。
ともかく、山を下りることにした。その場で読むには、その手紙、ぶ厚すぎた。何が書かれているにしても、いったん山を下りて、どこか、すぐに休めて、酒でも飲める場所がほしかった。尋常ではないのだから、態勢を立て直して、じっくりと読める環境が必要だと聖世は焦っていた。