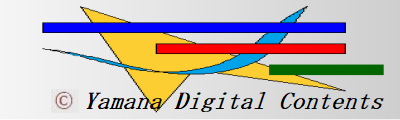カバヤキャラメルの秘密
小学校の四・五年生のころだったと思う。ぼくらに人気のあったキャラメルに「カバヤキャラメル」というのがあったキャラメルとしては、森永・明治・グリコが有名で、味もよかった。しかし、カバヤには中にカードが入っていて、これに絵と点数がついている。たしかチータ一が一点、ターザンが三点だったように思う。何点か集めると、点数によって景品がもらえた。なかでも、「カバ大王」というのは50点で、これを当てると「カバヤ文庫」という単行本がもらえた。しかし、これはまず当たらなかった。
何よりもぼくらがねらったのは、カバである。これが当たると、もう一箱その場でキャラメルをもらえたような気がする。あるいは10点くらいの点がついていたような気もする。 さて、単にキャラメル一箱を買うわけではない。さんざん選びぬいて、このカバを当てるのである。このキャラメルの箱には、左上だったか右上だったか忘れたが、隅の方に、小さいけれどカバが大きく口を開けている絵がついていた。その背中に「KABAYA」と文字がついていて、一体として商標のようなマークになっていた。この絵と文字の状態から、中のカードがカバであることを見ぬくのである。 そんなことができるはずがないとだれも言う。現に、店のおじさんもおばさんも、「どれでも同じだよ」と言っていた。大人は「どれも印刷やから変わらへん」「中にカードを入れるのにいちいちマ―クなんか見てるはずがない」といっていた。しかし、ぼくを含めて、近所の子供の何人かは頑としてマークとカードの関連性を疑わなかった。
一箱が一O円だったと思う。お菓子屋さんへ行くと、底が浅くて大きな、餅舟のような箱に山盛りにして積んであった。その中から、一つ一つ小さなマークを点検して、カバのカードが入っているはずのキャラメルを探し出すのである。10分、20分探すくらいざらである。全部見ても気にいらなければ、買わずに別の店に行くことだってあった。どんなマーク(ぼくらは「しるし」といっていた)が当たりになるかは、言葉ではいえない。一律ではないし、時々変ったりもする。その情報を手に入れるのがまたたいへんだった。
ぼくらからすると、かなりお兄ちゃん格の「名人」がいた。この人に運よく会えれば、一緒についてきてもらう。そこで、一緒に探してもらうのである。名人が「『K』の字の太いのがいい」とか「『Y』と『A』の字の問がひっついているのがいい」とか指示をしながら、一緒に選り分けてくれる。最終的に二・三箱にしぼられてくる。たまたま買い物に来た大人は、「そんなもんでわかるわけがない」とか「もういいかげんにしなさいよ」とかいいながら、それでも帰らないで見ている。最後の一箱を、名人が選ぶが、ぼくには確信がない。大人は、「五十分の一や」とか、「当たらへんだったらどうするんや」とかいうが、結果は気にしていたに違いない。名人は「絶対にまちがいない」と言い切る。この人がこういったときは、まず外れない。店のおじさん、おばさん、客の大人が注視するなかで、ぼくはドキドキしながら開けることになる。上蓋を聞いて、箱の両端を手で挟むようにすると、長方形の口がやや楕円形に拡がる。キャラメルと箱の内側にスキ聞が空いて、そこに狭まっているカードが見える。色だけでわかる。「カバ!」。正直、ぼくは、ホッとする。名人もたぶんそうだったと思う。
ぼくらのしていたことは、常識に対する挑戦なのである。さんざんに「当たりっこない」常識論と科学的理由を聞かされながらの行為である。ぼくらの言い分と正しさが証明されなくては立場がない。しかし、ぼくは大人たちがどんな反応をしたか記憶にない。多分、子供の勝利を認めたがらなかったのだと思う。確率的にあり得るとのことで、外箱のマークから中のカードを見ぬくという子供の技術を認めることはなかったと思う。
それにしても、カバを当てるのは一度や二度のことではなかった。「間違いない」と感じた場合は、たいてい当たった。はずれることもあったが、数学上の確率よりは格段に高かったのは確かである。 この当たりを見分けるポイントは、カバの絵とローマ字書体の特徴にあるのだが、何故かこれが少しだけ異常なのである。印刷技術のまずさから、多少変形したマークになることはあり得るが、それに当たりが入っているというのが不思議である。当たりカードを入れる箱だけは別の所で印刷して、他の外れの箱に混入させて出荷していたのかとも考えるのだが、同じものを印制すれば済むことで、わざわざ別の印刷をするとは考えにくい。もっとも、この頃の印刷技術は今ほど精巧でなかったようで、形の上で違いのわかるマークは二〇に一つくらいはあったように思う。その中でも、当たりには一種の型があった。これを見ぬくのがぼくらの技量であり、その技量の高さが自慢のタネでもあった。名人格のお兄ちゃんに教えてもらう。友達の経験を聞いて情報を交換する。そして自分が当てた外箱は残しておく。そうして自分の技術をみがいたものだった。しかし、最後はカンで決めた。もっとも、ギリギリの二者択一に悩むほどなら、どちらもアタリだった。
ぼくらは、何となくカバヤの会社と知恵くらべをしているような気持でいたが、もし会社が、意図的にマークと当たり力ードを関連させていたのだとしたら、そして、それを公にせず秘かに楽しんでいたとしたら、キャラメルの箱をかき回して、一心にマークを見比べているぼくらの姿をどんな風に想像していただろう。きっとマークに秘めた遊び心のメッセージ受信者に微笑んでいたに違いない。もしそうなら、単なる運ではなく技術で当たりを当てる楽しみをぼくらにくれたことをありがとう。それが秘密であったが故に、大人は参入せず、子供だけが理解しあえる宝さがしの遊びを与えてくれたことに感謝する。森永や明治がいかに甘くておいしくとも、カバの当て方について激論し、研究し、懸命に選りあさったカバヤキャラメルには強烈な思い出が残った。カバの形そのままの自動車が街の中を走っていて、そのうしろからついて走ったころの思い出である。
平成4年(1992年)2月 奔馬第15号