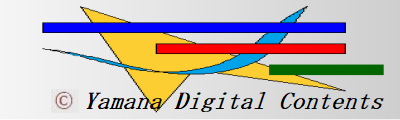カバヤキャラメルの仲間たち
ー再びカバヤキャラメルの秘密に迫るー
先稿「カバヤキャラメルの秘密」を書き上げてから、面白い記事を発見した。高橋幸子「カバヤキャラメル」(昭和五九年九月二九日京都新聞朝刊〉である。景品や見分け方についてはぼくの記憶とかなり違うところがある。しかし、ぼくの記憶も暖昧だし、右の執筆者も「記憶は正確ではない」と断っている。この際、それはあまり問題でない。何よりもぼくが嬉しいのは、「外側からアタリを当てる」子供たちが紹介されていることである。やはり仲間はいたのである。先稿はぼくの記憶のまま置いておくことにして、文筆家が描いた風景と心情を引用しながら、カバヤキャラメルの秘密について再び想ってみたい。
昧は忘れているのに、カバヤキャラメルのアテモンの味は覚えている。
子供たちは、・・・カバの絵が描かれていた箱を四方くまなく研究し、外側からどれがアタリかを当てる、いわばセミプロだった。
そうなのである。シロウトは、ただ運にまかせて一つをつかみ取るだけであった。無造作に取って幼児に買い与えている母親は、ぼくらから見れば10円を浪費しているバカでしかなかった。アタリを見つけるキーポイント部分は、高橋幸子氏によれば「カバの足」だった。この点、「KABAYA」の文字が決め手と思っていたぼくも、それだけではなく、「カバの足」も確かにポイントになっていたことを思い出した。カバの絵は重要だったのである。だから、今でもハッキリと絵柄は憶えている。
二本の後ろ足がくっついているのがもう一個、心もち右足の長いのが大当たりと情報は乱れ飛んで、子供たちは駄菓子屋さんの力バヤキャラメルのコーナーに群がった。
カバの足を点検しては別の箱をとり、また点検しては別のをとり、大箱に行列したカバヤキャラメルはたちまちおもちゃ箱みたいに引つくりかえったが、店番のおばちゃんは『へぇ、そんな足でアタリがわかるのか』と、さも感心したように驚いてみせた。
粘りに粘って足の調査はしたけれど、しかし今思えば、カバの後ろ足がくっついているような、いないような、右足が長いような、左足が長いような、印刷がぼやけてはっきりしない箱ばかりだった。
確かにカバの絵(マーク)は小さかったから見にくかった。箱紙の質も悪かったのだろう。刻印されたような絵と文字は微妙に違って均一ではなかった。しかし、その違いに特徴を認めてアタリを当てたはずである。高種辛子氏は、大人の目でふり返っている。常識の枠内で、理屈に合った科学的分析をしている。それこそが、あの頃に大人や物知り顔をしたオトナ子供がぼくらにあびせた科学的見解そのものではないか。
考えると、問屋から来る大箱の中に、大当たりがいくつもあるわけがない。ひとり当たれば、おしまいだったのではないか。第一、箱は手描きでなく印刷である。カバの足がわずかにちがうように見えるのは印刷のズレだろう。いちいちズレを見て大当たりを決めるほど、カバヤの工場の人が優雅だったとも恩えない。
氏がいっているのは、子供のころの無知の反省だろうか。大人になって、本当のところはこういうことだったのだと納得してもらっても困るのである。どんなに非科学的であっても、ぼくらは「カバの足」に秘められたメッセージを確かに受け取っていたと信じる。常識の外にあった事実にこそこだわりたい。
もっとも、氏にはぼくらと決定的に違う経験がある。
しかし、やっと購買権を得た子が10円出し、自信の箱をあけると、たいていスカだった。
ここに氏がカバの足の秘密を認めようとしない理由がある。せっかくその秘密に気づいていながら、どれがアタリの足かを見ぬく技量を持たなかったのである。たぶんそれは、正確な情報を教えてもらえなかったからであろう。ぼくらもこれが絶対のポイントというものは最後まで明かさなかったし、秘中の秘というものが確かにあった。そして、「あいつはよう当てよる」「名人や」という評判をもらう連中は、たいてい当てたのである。だから、今でも氏の論には賛同できない。カバの足に、KABAYAの文字に、アタリを暗示するシルシが確かにあった。
とはいえ、ぼくが「カバヤの秘密のメッセージ」と感じたことを、氏も同じように感じていたのは驚きであったし、いよいよぼくを確信させた。
カバの足に暗号を感じたのは、子供たちの片想いであったはずだ。私たちは、テストの点がわるくても決して自分の努力が足らんのだとは反省しなくとも、自信の箱がスカだと、カバの足を見る自分の技量がまだ足らんのだと反省した。
氏がカバの足に「暗号」を感じたのは正しかったのだ。それを「片想いだったはず」と断言してもらっては困る。
カバヤがそれほど大きな会社だったとは思わない。「カバの車」をつくって走らせていたように、どこか大量生産とは縁がなさそうな気がする会社であった。案外、町工場なんかで、アタリカードを詰める役のおじさんがいて、意識して印刷ズレの箱に「当たりのカバ」を入れていたのかもしれない。「子供らよ、これを見ぬいてごらん」というぼくらへのメッセージを込めて。ぼくらはそれをみごとに受けとめたのではなかったのか。高橋幸子さん、あなたは、ご自身がおっしゃるように、「カバの足を見る自分の技量がまだ足りなかった」のです。
平成4年(1992年)2月 奔馬第15号