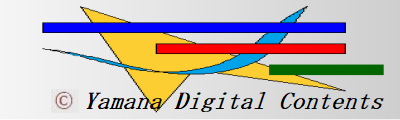一 つくられた偶然
妙なすれ違いや出会いが何度かあった。本当に偶然なのか、偶然を装っていたのかわからなかった。
その度に動揺した。平気を装ったけれど、心拍数は跳ね上がって胸が苦しくてたまらなかった。動揺しないはずがない。
だって、そうだろう。もう二年以上も逢ってないのだ。会いたくて、逢いたくて、たまらなかったのに。
それに、おまえからまだ聞いていない。「さよなら」も、「嫌いになった」とも、「ごめんなさい」の一言さえ。ぼくには未だ終わってなかったのだ。
たしかに、おまえはぼくから離れて行った。逢うことをやめた。連絡を断った。話しかけても無視した。近寄れば避け、見たら逃げた。すべてのつながりが途絶えてから時が経った。しかし、それで「終わっている」というのはおまえの理屈に過ぎない。ぼくには、おまえが終わらせようとしているところで止まったままだ。
なぜ終わらせようとするのか、その理由を聞いたことがない。なにも理由を告げず、別れの言葉もない。思い当たることはなかった。あるとすれば何らかの誤解。それなら解くことはできた。おまえと話すことさえできれば。
すべてが拒絶されて狂いそうだった。おまえの家の前に立って大声で喚きたかった。悲鳴をあげたかった。理由を言えと迫りたかった。話を聞けと怒鳴りたかった。
だが、なにもしなかった。哀れみなどいらない、蔑まれることは拒否すると強がった。そして二年も経った。悲しみが癒えることも怒りが鎮まることもなかった。
ぼくが通るとわかっている場所におまえは現れた。頻繁にではない、ほんとうに偶にであった。だが、もしかしすると、それはぼくが帰りの時間を遅らせたからかもしれない。早めたからかもしれない。それが続くと、またおまえとすれ違うことがあった。会わなくなって二年の間、ぼくの視界におまえが現れたことはなかったのに。つくられた偶然との疑いは確信に変わった。
動揺は隠してすれ違った。いつもおまえは薄く笑っていた。おまえが意識していることはこれで明白だった。ぼくに声をかけさせようとして、それを待っているとしか思えなかった。
ぼくは期待してしまった。おまえはやっと理由を話そうとしているのではないか。もしかして謝りたいのではないか。そのきっかけを誘っているのではないか。
しかし、ぼくは声をかけるのを躊躇った。恐かったのだ。
声をかけたとたん、『ナンパ!』と嘲笑されたらどうしよう。薄笑いしながら無視されたとしても同じだ。そういう侮辱に耐えられないのはおまえが誰よりも知っているはずだ。
ぼくは遂に声をかけた。おまえの名を呼んだだけなのに、懐かし過ぎて舌がもつれそうになった。緊張で声が震えた。顔は強張っていたにちがいない。
しかし、おまえは嬉しそうな笑顔で応えてくれた。問題など欠片もない恋人のように。それはぼくにだけ見せる恋人の笑顔だと思っていた。ぼくは、元どおりになれるかもしれないと思った。おまえの笑顔はそう思わせるほどわだかまりがなかった。
今も忘れないあの日のことはここから始まった。
二 あの日
二人で夜の河川敷を歩くことになった。前日からの雨は昼過ぎに止んでいたが、人影はほとんどなかった。
おまえは大人の女になっていた。自信にあふれて堂々としていた。大きな紫陽花のプリント柄のワンピはおまえに映えた。ウェストの締まりが強調する胸に目がいく自分が恥ずかしかった。だが、その化粧は気にいらなかった。嫌だった。大きくて愛らしい瞳とくっきりと濃い眉毛になんのメイクもしてほしくなかった。清潔で可愛い唇が紅で穢されているような気がした。それでも、好きでたまらないおまえに変わりはなかった。芯はぼくが恋した少女のままと信じていた。
ドクン、ドクンという心拍音をおまえに聞き取られそうで恥ずかしかった。あのころは、逢えたときは二人ともそうだった。そのことがとても幸せだった。
訊きたいことはいっぱいあった。何から訊こうか、なんと訊けばいいのか、そんなことばかり考えていた。考えてはいたが、言葉にできなかった。こんな日が、こんな場面が来るとは思ってなかった。覚悟ができていなかった。
おまえは饒舌だった。よく喋った。現在がいかに充実しているかを心底楽しそうに話した。
話のなかに『彼氏』がいることをほのめかした。嬉しさを隠さなかった。
それが言いたかったのか。それを聞かせたかったのか。
必死になって興味のないふりをした。正直にいうと、とっくに予感していたことなのに落ち込んでいた。当たってほしくない予感ほど的中するというのは本当だ。だから聞きたくなかったのに、おまえは嬉しそうに彼氏のことを打ち明ける。ぼくは、落胆と動揺を見透かされまいと必死だった。
おまえはぼくの無関心が意外だったにちがいない。不意にお喋りをやめた。戸惑ってはいたが、ぼくの落胆には気づかなかったようだ。なにかを考えるようにして黙って歩いた。ぼくはおまえに歩調を合わせて歩いた。
水量を増した川の水音だけが聞えた。暗がりに溶け込んだ広い川面は街灯の淡い色を映していた。暗くておまえの表情まではわからなかった。
二人とも黙って歩いた。
ぼくが話したかったのは過ぎた日のことだった。
あのころがどんなに素敵だったか。
何を見て、何を話したか。
それなら、いつまでも、何時間でも話し続けることができたと思う。
あのころに戻れるなら、もう、離れていった理由などどうでもよかった。すべては水に流せた。
しかし、おまえにそんな気がないことはわかっていた。この偶然は、二人が終わっていることを念押しするためにおまえがつくったものと、もうわかっていた。持ってはならない期待を持ったがために虚しくされた。的中ってほしくない予感が的中って落胆している。こんなことのために、おまえはこの逢瀬を設定したのか。
黙っているぼくに見切りをつけて、おまえはまた喋り始めた。
ぼくは黙ったまま歩いた。
おまえは、ふと立ち止まって、俯いてなにか考えるような仕草をしていたが、顔をあげると、思い切ったように訊いた。いや、それは訊いたのではなく、単に言ったに過ぎない。
「新しい彼女はできた?」
やっと本題に入ったのだ。言い出すきっかけがつかめなかったので焦っていたのだろう、急きこんで続けた。
「わたしは好きな人がいるの。つきあっているの。あなたにも早くそうなってほしいの。変わってほしいの」
言葉は別にして、おそらく、こういうことをいうのだろうと思っていた。でも、「変わってほしい」はないだろう。「変わらないで」と言ってたくせに。
「ぼくは変わらない。約束したことだから」
そう。それは約束、それは誓いだった。心変わりはしないという。
自らがしないというのではない、しないでという相手の願いを裏切らないという約束だった。おまえがそれをぼくに誓わせたのだ。「変わらないで」とともに。
おまえはそれを忘れていなかった。だから気にしていたにちがいない。
「もういいじゃない。約束で縛るなんて無理なんだから。そんなこと続けるなんて無理!」
「約束だから変わらない。君も同じでいてほしい」
なんと馬鹿なことを言ってるのだろう。心変わりをして裏切った女に向って、自分は変わらない、おまえもそうでいてくれとは。しかし、これ以外に答えは持っていなかった。たぶん、おまえはぼくのこの答えを予想していたのだと思う。
「変わってよ!もうわたしのことは忘れてよ。きっと新しい恋人が見つかるって!そうなってください!そうなってほしいの!」
これだけを吐き出すように言い終えると、おまえは一仕事終えたようにいった。
「これが言いたかったの。やっと言えたわ。よかった。ホッとした。気になってたの。」
おまえは自分の言葉に酔ったように満足していた。そして一人でうなずいていた。
そのとき、ぼくの中で堪えていたものが切れた。始めておまえを憎いと思った。「身勝手」「理不尽」「不遜」「傲慢」「裏切り」という思いが頭の中に湧き出して溢れ出した。それが塊になってぼくの内側で暴力へと変化した。制御できない力が熱を帯びてぼくを突き上げてくるのを自覚した。
足もとの砂利がきしむ音がした。ぼくはお前の正面に向き合った。すぐ前におまえの顔があった。
おまえは一瞬だけ訝るような表情をしたが、すぐに笑顔になった。何かを言いかけたとは思った。
右の腕が飛んだ。掌がおまえの左頬を張り倒して振り切れた。
湿った音とともに確かな手応えがあった。
おまえの上半身が大きく傾いだ。張られた左の頬を掌で庇いながら、上半身は捩じれていた。掌で隠した頬に自慢の長い髪が覆いかぶさっていたが、その隙間に驚愕するおまえの顔をはっきりと見た。
おまえは一・二歩後退りして傾いた身体をやっと立て直した。強がって笑おうとするが顔が強張っていた。
そのときおまえが放った言葉を忘れたことはない。
「すっとした?」
もう、笑うしかない。
全身の力が抜けてしまった。制御できないと思った暴力はあっけなく抜けた。
憎悪も怒りもしぼんでしまった。
三 復 讐
これで二人は完全に終わった。
この日とこの一言をぼくが忘れたことはない。
思い出す度に、疼くような幸せの記憶までも一緒に連れてきてくれるのだ。
たしかにぼくは笑った。声を出さないで嗤ってしまった。
それでおまえは立ち直れなかった。
ぼくは無言でおまえを見下ろしていた。
短い時間が過ぎた。
耐えられなくなったおまえは泣き出した。必死に抑えても嗚咽は漏れてしまう。聞かれたと思うから屈辱は増幅する。その屈辱におまえは肩を震わせていた。
ぼくは、おまえを置いて、来た方向にゆっくりと歩き始めた。堰を切った泣声が後ろに聞こえていた。
最後まで晴れなかったぼくの疑念だが、もう吹っ切れた。おまえがぼくから離れていった理由を今さら知ったところで何の意味もない。口惜しさも怒りも嘘のように消えてくれた。まだ見ぬ男に嫉妬することもない。女を殴った負い目さえ、あの一言が消してくれた。後悔など欠片もない。
おまえは悔やんだろう。口惜しかっただろう。もう少しでおまえの描いたストーリーは完結するところだったのに、最後は捨てられた女のようにおまえは惨めだった。
四 特別な思い出
あれから、年単位の時間が過ぎた。
何年も何十年も経った。
これまでに、なんとなく節目でおまえに出会ったことがあるけれど、これはまちがいなく偶然だった。百万都市にいながら、何年か、何十年かに一度の出会いは縁ある二人だったからと信じよう。
繁華街のアーケードの下ですれ違ったときは、おまえはすれ違う男が振り返るほどいい女だった。ぼくが恋した女だもの。一緒にいた男も誇らし気に見えた。ぼくは小さく笑って軽く右手をあげて挨拶した。動揺しているおまえが可笑しかった。
電車の中で会ったおまえは疲れた顔をしていた。隣の冴えない男がおまえの疲れの原因だろうと失礼な想像をしてしまった。
これが神の差配かと思う偶然があった。ぼくが恋人と一緒のときにお前と出会った。すれ違いではなく、お洒落なレストランのなかのこと、おまえに逃げ場はなかった。離れた席にいるおまえはぼくらの方を盗み見ていた。目が合うと、ぼくは笑顔で応えた。おまえはこの店に似合わないオバサンでしかなかった。ぼくの視線の先を恋人が振り向いたとき、おまえは目を逸らせて小さく縮んだように見えた。
不思議そうな顔を戻して可愛く頸を傾げた彼女に、ぼくはただワイングラスを合わせた。何かを問いたげな彼女だったが、笑顔に戻って応じた。恋人に語ることではない。
恋人と飲むワインと料理はとても素敵だが、おまえが思い出させてくれるあの一言とそれに纏わる記憶がもたらしてくれる愉悦にはまた別の悦びがある。
妙な言い方だが、あの一言とあの記憶は、思い出す度に嬉しくて笑いたくなる。誤解されそうだが、一人でいるとニヤニヤしてしまう。心地よく疼くような幸せ。例えるなら、自分一人だけが試験に合格したときの飛び上がりたいほどの歓喜を、一人で、心ゆくまで反芻するときの幸せに似ているかもしれない。密かに思い出し、反芻し、噛みしめて味わう。やにさがるとしても人前でなければ許される。
恋人の前では、それも含みのない笑顔に転化できる。彼女はぼくの笑顔に笑顔で応えてくれる。おまえとのこの特別な思い出は、ぼくと彼女を幸せにしてくれる。しかし、それを彼女と共有することは決してない。
おまえもまたあの日とあの一言を今も忘れてないにちがいない。忘れたくても忘れられないにちがいない。
時が経っても、年月が過ぎても、齢をとっても、忘れることはなかった。
二人とも同じ記憶を忘れないできた。これもまた思い出の共有というロマンにしてしまおう。
おたがいが「あの日」「あの一言」をキーワードにして蘇る記憶という名の思い出。
それはぼくの酒の肴、愉悦の味、幸せの供。
おまえには…
ざまぁみろ! すっとした!
終