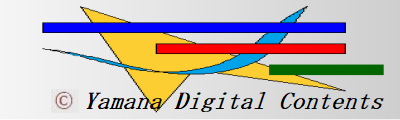果たさざりし辞典
山 名 隆 男
若くして他界した作家高橋和巳(享年39歳)のエッセイに「果たさざりし辞典」というのがあった。短いエッセイだが、このごろ、しきりにそれを思い出す。思い出すけれど、本棚をかき回しても、それを掲載していたエッセイ集は見つからない。「孤立無援の思想」という標題のエッセイ集であったとおもうが、だれかが「かして」と言って持って行ったままのようにおもう。だから、もちろん正確ではないが、記憶にある内容を言ってみるとこういうことになる。
和巳がある友人と碁を打っていたときの話題である。突然その友人が「『果たさざりし辞典』をつくろう」と叫んだ。和巳が聞いた「項目別か、年代別か」。友人が言った。「いや、人名別だ。各人が、かつていかなることを想い、理想としたのかを記し、そしてそれがいかなる経緯といかなる理由により破綻し、実現しなかったのかを書き留めるのだ」。和巳は「なんと哀しいことをいう奴だと、その友人の目を正視できなかった。
しかし、「苦悩教の教祖」といわれ、「陰々滅々」と評された彼に、「果たさざりし」何ものもなかったとは信じがたい。期待は裏切られるもの、夢は砕かれるもの、未来は挫折と同意義だと説く小説を出し続けたのは彼ではないか。安っぽい青春賛歌よりも、よほど響くものがあったからこそ、われわれは彼に共感し、彼の作品を好んで読んだ。その彼が、何故この「果たさざりし辞典」に共感しなかったのか、当時から今に至るまでわたしの疑問である。彼は、人がその人生の終盤において累々たる挫折の経歴をかかえるであろうことは知っていたに違いない。ではあるが、なお壮年の域にある友人が、早くも何事かを為し得なかった言い訳をするが如き発想を哀れと思ったのだろうか。皮肉にも、彼こそ病魔という障碍に倒されて、想い半ばで「果たさざりし」志をこの世に残して滅んでいくことになる。
わたしは、彼のこのエッセイを読んだとき、そういうものがあってもいいとおもった。今では、なお一層そう思う。その当時のわたしは彼よりも若かったが、果たさざりしも何も、それにあたいするだいそれた夢とか希望があったわけでもない。ただ、そんなものを持っていたとしても、まず絶対と言っていいほど叶えられないものであることは既に知っていた。世俗的な願望でさえ、やっと手に入れても、満足できることは稀であるうえに、必ず何かを諦めた代償でしかないことも。しかし、難儀なことに、人は想いのどこかで期するものを持っているのも事実である。若いときはそれを口にしても恥ずかしくはない。人はそれを嗤いはしない。できそうもないことでも許してくれる。だが、決して実現することなどない。あがいても、努力しても、どうにもならないまま歳をとり、なにごともなく、何も起こらず、何も変らない大人と俗人の群れにまぎれていく。なぜ想いは果たせなかったのか。運がなかった。金がなかった。想いを評価できる力量が世間にはなかった。才を見抜く人にめぐりあわなかった。家庭が、家族が許してくれなかった。…。そう、果たさざりしには理由がある。しかも自分には如何ともしがたい。念を残すのはそれ故である。成し遂げようとしなかったのではない。これこれ、しかじかで出来なかったのだ。そう言いたいのだ。しかし、それを愚痴だとか弁解がましいと切り捨てることはない。聞こうではないか。何を想い、何を期し、何を成そうとしたのか。単なる願望とか欲望が叶わなかったという話ではなく、もう少しレヴェルが高いもの。理念があり、ロマンがあり、意味があるものなら、果たされることに個人を超えた社会的意義があるはずである。それが偉大な所業になるはずのものなら、誰かが継げばいいではないか。素晴らしい理想なら、みんなで共有すればいいではないか。それを知るだけでも価値がある。そして、なによりも、胸中奥深く沈殿しているその果たさざりし想いの亡骸に葬儀を出してやることにこそ意味がある。一度は心のなかに、胸のうちに生きていたに違いないのだから、それが「死ぬ」と表現しても、「骸」になったと言っても、文句はあるまい。果たさざりし辞典はその鎮魂になるはずである。おびただしい葬列に、はたして我々は畏れるのか、感動するのか。
「奔馬」 第 31 号 2004.1所収