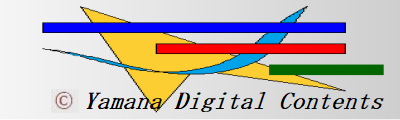第二部 生き恥
注 「奔馬」掲載稿では、何故か二部構成という形がなくなって、「七 時を経て」「八 想い邂逅」と続きます。しかし、元々は二部構成だったはずです。これも補正版です。
一 時を経て
聖世はその屋敷の大きさに圧倒されていた。すべてが木造の古風な造りであった。入口はさほど幅広くもない格子戸造りであったが、板塀は屋敷を大きく囲っていた。入口に威圧感はなかったが、聖世は古く黒ずんだ表札を見上げたまま立ちすくんでいた。表札には「刀環雪絵」とあった。ただ、入口の格子戸の棧にしつらえてある郵便受の下には、雪絵とは別の女性名を書いたプレートが掛けてあった。棧の隙間の奥に古風な家の玄関口が見えた。古い木造の建物ではあるが、上質の資材で建てられているのがわかる重厚な屋敷であった。聖世は事前に電話さえしないでここに来ていた。大悲山から下りて、もう二〇日が経っていたが、何も変わりはなかった。
聖世は、この屋敷の主に会ってみたくてやってきたのであるが、電話もしなかったのは、やはりためらいがあったからである。とりあえず、刀環雪絵の家を確認してみよう。それだけで今日は帰ってもいいと思っていた。彼女の家は屋敷然として実際に存在した。装飾めいたものがまったくない、いかにも旧家のたたずまいは、ここの住人とは住む世界が違うように思われて聖世を尻込みさせていた。
そのとき、奥の屋敷の玄関戸が引かれて、着物の女性が心地よい下駄の音をさせながらこちらに小走りで駆けて来た。聖世は一瞬逃げ出しそうになったが、怪しい訪問者のぶざまな姿が頭をよぎった。それで思い直してとどまった。格子戸の上に防犯カメラが設置されているのを見てしまったのである。もう自分の存在を知られているのは疑いようがなかった。格子戸の内側の鍵がカチッと音を立てると、カラカラと軽い音とともに引かれて、腰を少し折った女性が戸口から顔をのぞかせて声をかけた。
「もしかして、聖世さまでしょうか」
気品のある若々しい女性である。着物をごく自然に着こなしている。聖世は、ただ「そうです」と答えるのが精一杯であった。
「お待ちしておりました。どうぞ、お入りくださいませ」
『待っていた』という言葉に固まってしまった。招かれるままに聖世は戸の内に入ってしまった。女性は格子戸を閉めると聖世の先に立って再び乾いた下駄の音を石畳に響かせながら玄関へと歩いていく。聖世はただ追いていくしかなかった。きちんと連絡してから、それなりの覚悟をして、手土産も用意して訪ねて来るべきだったと悔いていた。これでは、礼儀知らずの若造のままではないか。四〇年を待っていてくれた「恋人」との初対面にしては、なんという失態をしてしまったのか。後悔と羞恥と整理のつかない気持ちのまま、玄関に招き入れられた。それにしても、この女性はだれなのか。雪絵本人でないことは確かなのだが。
広い和室に重厚な座卓。部屋から手入れの行き届いた庭が見える。午後の淡い陽が射しこんで部屋は明るく心地よかった。
聖世は、刀環優貴のゆったりした口調の話を聞いていた。ひたすら、聞くばかりであった。そうするしかなかったのである。
雪絵は二年前に亡くなっていた。聖世は既にここで言葉を失っていた。六八歳であったという。今生きていれば七〇歳ということになる。先ほど、聖世から願って仏前にお参りさせてもらった。仏壇の脇の台に雪絵の写真が置かれていた。白髪が上品で美しい女性であった。凛とした顔だちはいかにも家柄の良さをうかがわせるものがあった。それは、目の前の優貴にも隠れることなく受け継がれている。
この女性、刀環優貴は、実は雪絵の妹の子・姪にあたるという。雪絵が好きで、京都の大学に進学したのを機に叔母と一緒に暮らし、遂には雪絵の養女になったという。雪絵自身は生涯を独身で終えたという。雪絵は、聖世の思い出を掘り出したころは規模の大きい女子学園の理事と教員をしていたというが、未だ三〇歳になるかならぬ歳だったことになる。
聖世と相対して正座している優貴は澄んだ瞳で聖世を見据えている。眼差しには力があった。聖世は思わず目をそらした。まとめた髪、聡明そうな額、形のよい鼻筋と上品な口元、そして透明な肌。目を合わせるのが苦しくなるほど気品のある美人であった。先ほどは気がつかなかったが、彼女の着けている着物には、淡いふじ色の下地に鮮やかな緑の葉をつけた薄いピンクの花があしらわれていた。帯には黄色地にあやめが染め抜かれ、彼女の背で大きく蝶姿に結ばれていた。華のなかに清潔な少女の香りがした。
ひととおり、雪絵と自分のことを話すと、優貴は、本題について話し始めた。聖世は、優貴が淹れ直してくれた茶をすすりながら、黙って聞くだけであった。
叔母さま…、あ、本当は養母ですが、私はいつもそう呼んでいましたのでお許しくださいまし。もう、聖世さまにお会いするのは叶わないと思い始めたのでしょうね。でも、楽しそうに語ってくれました。
叔母さまがいうには、本当は、こんな人の秘密はだれにも話さずにおくべきなんだけど、自分が亡くなった後のことを思うと、人の大切な思い出と秘密を黙って持ち帰った者として、そろそろ対処をしておかねばと思い始めたということです。叔母さまは、確かにお躰は弱っていらっしゃいましたが、特にどこが悪いというわけでもなかったので、私は叔母さまが亡くなるなんてまったく思ってもみませんでした。ですから、これまでお大事にされていたことを私に託ける言い訳のためにそのようないい方をされているとしか思いませんでした。でも、とても真剣な顔でおっしゃるものですから、私も真面目にお聞きするふりをしました。本当は真剣に聞いてなんていませんでしたけど。 叔母さまから、聖世さまの思い出の箱を大悲山から掘り出したこと、そしてお手紙を箱にいれて埋め戻したこと、そのお手紙の内容などを話していただきましたわ。でも、聖世さまが実際に何を書き残されていたのかについては、具体的には話していただけませんでした。ご自身の想いに誠実に生きる覚悟を記されたものと私は想像しておりました。叔母さまは、ご自分にも重なるところがあることを特に大切にされておられたと思います。そして、叔母さまがもし亡くなられていても、聖世さまが来られるようなことがあればお返ししてほしいと、厳重に封をした包みを渡されました。もちろん、それが聖世さまの大切な思い出のものだということはわかっておりました。
でも、まだまだ叔母さまはお元気でいてくれると疑わなかった私は、それほど重くは受けとめませんでした。本当に、叔母さまが亡くなられるなんて…想像できませんでした。それに、お話を聞いても、単に失恋した愚痴を負け惜しみに置き換えている男の人にしか思えませんでしたもの。ゴメンなさい、こんないい方をして。それは、聖世さまの思い出つづりがどんなものか存知上げなかったからかも知れませんし、叔母さまのご経験に思い至らなかった私の愚かさとも思います。ですが、このことは、今なお私には充分に納得できないままです。ただ、それは叔母さまの生き方が、人生の在りようが、あまりにも私らとは距離があるからだと思います。それは、叔母さまが亡くなった後に私に読ませるための手紙を遺されていたことと…叔母さまの突然の死で、改めて思い知らされました。私には叔母さまのような生き方が素晴らしいとはいえても、もったいなくて、さびしくて、悔しくてならないのです。もっと、もっと、幸せになれるのに、なる権利があるのに、それを捨ててしまわれているのですもの。それは、聖世さまを見ていると余計に思ってしまいます。最初に恋した女性との誓いを破って、まったく違う人生を生きておられるのでしょう。それって叔母さまとはまったく反対ですもの。失礼ですが、その程度のことは存じ上げています。叔母さまは、決してそういうことをしないように厳しくおっしゃっていましたが、私は、叔母さまがお話してくださったときから、聖世さまが京都で弁護士としてご活躍のことはインターネットなどで調べて知っておりました。叔母さまにはそのことだけはお教えしてあります。でも、叔母さまは、聖世さまのことをそれ以上内緒で調べるようなことは、もうしてはいけないときつくおっしゃってられました。私はそんないいつけなんて、場合によっては無視するつもりでいました。こんなに長い間放置されている思い出って何だろうと疑いました。忘れておられるのなら、思い出させて山に行かれるように仕向けてみようかとか、私が直接に聖世さまにおはなしして叔母さまを訪ねていただくようにお願いすることさえ考えたこともあります。でも、やはりそれは叔母さまの意思に反することですからできませんでした。そんなことをしても喜んでくださらないですものね。
叔母さまが亡くなられたときは、本当に悲しかったです。もう、そんなことはどうでもいいことのように思ったものです。それなのに、叔母さまは、亡くなられてから読ませるための私宛の手紙を書いておられました。聖世さまと、聖世さまの想いの形見のこと、それを私に託することが書いてあります。それを読むと、いっそう、叔母さまが可哀相になって、聖世さまを恨みました。
優貴が目元を潤ませるのを正視できずに聖世は俯いていた。ただし、言い返す言葉がないわけではない。そうではないか。自分が捨てたものを無断で掘り出して、勝手に自分のことを想像されていただけなのに、何故自分が責められるのか。
しかし、聖世に後ろめたい思いがあるのも事実である。ホステル日誌にその存在をほのめかすようなことを書いたのは迂闊であった。それがなければ、こんなことは起こらなかった。なにより、聖世は自らに課した誓いをことごとく破ったことに弁解できないことを自覚していた。誓っておりながら、だれにも知られていないことをいいことに、後ろめたささえを覚えることなく反故にしてきたのだから、優貴に言われるまでもなく卑怯者の誹は免れない。雪絵も優貴も、聖世の誓いを聞いたのと同じなのだから、二人に対してだけは、聖世は誓いをまもらねばならない男だったのである。
だが、たとえそうであっても、聖世の誓いが雪絵の人生にどのようにかかわるというのか。知らない男のただの独り言を聞いたのと同じではないか。しかも、誓っても、約束しても、なにひとつ守れなかった、弱くてだらしない男だった。雪絵はそんな自分を見ないで済んだのだから、むしろよかったのではないか。聖世自身もそれで救われたことになる。優貴は、聖世の堕落をとうに知っていたのだから、失望などすることもないではないか。
頭ではそう反駁しても、まだ聖世は顔を上げられないでいた。優貴の怒りに呑まれていたのである。
じっと聖世を見詰めていた優貴は、封書を座卓の上で滑らせて聖世の前に差し出した。卓が大きくて優貴の帯から下は見えないので、その封書がどこから出てきたのか聖世はわからなかった。おそらく、彼女の正座している膝の脇にでも置いてあったのであろう。着物の女性でも、一番美しい正座姿の膝元が見えない。それをぼんやりと想像している自分がいる。こんな時にこんなことを想像している男に過大な評価も期待もあるまい。優貴に見透かされているに違いない。聖世は、自分の自堕落を告白して謝るしかいないと覚悟して顔を上げた。しかし、背筋を伸ばして、まっすぐに聖世を射抜く優貴の瞳と遇うや再び聖世は羞恥に顔を伏せてしまった。黙っているのは息苦しいのだが、何をいっても場違いで、とって付けたような言い方になるような気がしたからである。そんな聖世を見詰めていた優貴がやっと口を開いた。
「叔母さまの手紙です。ごらんのように私宛ててです。私が疑って、反発して、怒ってさえいたことをご存知だったからこそ、こういう遺書のようなものを遺しておかれたのでしょうね。私がおはなしするよりも、叔母さまのことをわかっていただくにはこれをお読みいただくのが一番かと思います。どうぞ、お読みくださいませ」
そういうと、優貴は茶托を引いて立ち上がり部屋を出て行った。茶を淹れ直すことを装っているが、おそらく聖世に対する配慮であろう。座った目線から見る優貴の起居姿の優美さに聖世は見とれていたが、優貴が敷居を越えたところの廊下でこちらを向いて座りなおすや、慌てて手紙に目をやった。優貴は丁寧に頭を下げた後、目を伏せて襖に両手を添えて閉めた。磨かれた廊下を衣擦れと足袋の音が遠去かる。大きな部屋に一人残された聖世は心細くなった。部屋には匂い袋の香りがほのかに残っていた。
改めて雪絵の手紙を見る。憶えのある字がつづられていた。
|
優貴ちゃん、あなたには叱られるでしょうけれど、死んでしまってごめんなさいね。でも、私はたくさん生きました。あなたが思うほどさびしいものではありませんでしたよ。あなたには本当にお世話になりましたね。あなたは、最愛で最高の娘でした。私があなたに教えたり、譲れるものがあるとすれば、もう残ってるものなどないくらいあなたは私から汲み取り、吸収してくれました。もう、思い残すことなんてありません。ただ、あなたには聖世さんのことが不満なのですね。ほんとうに、こんなこだわりって、自分でもおかしいと思うわ。見ず知らずの方が捨てた物に縛られたり、すがったりしているのですものね。でも、もちろんそれは物ではないのよ。ひとの想いなの。それって、私にとってはとても大事なものだったの。
聖世さまには、もう、あなたのいうとおり会えないと思っています。こんなに長い間、あれだけの思い出のものを、とうとうさがしにはこられなかったのですもの。捨てたものは振り返られないのでしょうか。あなたはいっつも「そんなもの忘れてるに決まってるわ」といってたわね。忘れてしまうということはないと思うけど、あの大悲山に埋めたものを甦らせたくないと思っておられるのだと思うの。それはそれでいいのだけど、私は見てしまったうえに、持ち帰ってしまったでしょう。そして、私の手紙を代わりに入れておくような、よけいなことまでしてしまったわ。それで、今日まで聖世さまを待ち続けることになったのね。もちろん、待つといっても普段は忘れていたわ。恋しい方を待っていたわけではないものね。ただ、手紙を入れたのには理由があったの。優貴ちゃんにはいってなかったけど、実は聖世さまのお相手の女の子は私が知っている娘だったの。そう、「女の子」です、うちの学園の子ですもの。ほんとうに、まさかの偶然なんだけど、こんなときって不思議な気持ちになるでしょう。私がね、一年近くも経ってからお手紙をつけて埋め戻したのはそういう事情があったの。 最初は、そのお嬢さんには隠していたわ。でも、自分から近づいて、いろいろお話をするようにしたの。自分で嫌なことをしているなっていう罪悪感はあったけど、やめられなかったわ。そして、聖世さまに対する彼女の仕打ちを知ってしまったの。許せなかったわ。でも、私には、彼女を叱ることも、たしなめることも出来ないのね。ただ、自分を聖世さまに置き換えて見てしまったの。そうする理由が自分にはあったわ。でも、哀れとか可哀相だと思われることなんてないの。愚かといわれるのは甘受するけど。そんなアッポちゃんがいてもいいと思っているし、私には聖世さまのようなお仲間がいたことが嬉しかったの。彼女は卑しく、醜悪に見えたわ。彼女はいうの。「気持ちが冷めていくときって、相手が誠実であることがたまらなく嫌なんです」って。そんな理不尽なことって許されないわ。誠実であることがなぜ嫌われるの。もちろん、人の心のことですもの、合理性とか理屈とかで測るものでないことはわかっています。でも、相手がどれほど苦しみ、傷ついているかに思い遣れるのがその人の品格というものではないかしら。突然に引いて、弁解もしないけど、会おうともしないで、会えば逃げようとして、追いつかれたら無視するなんて、何がなんだかわからない相手の戸惑いさえ惟わないのかしら。それでも、私の知るところでは、聖世さまは嫌味も愚痴も彼女にはぶつけておられなかったわ。追っても、拒絶されていることを知ったら、そこからはすべてを心の内に納めてしまわれたように思います。彼女から何の弁解も説明もないままよ。どうして心変わりがしたのか、想像するしかないわね。あらゆる可能性を想像されたはずよ。でも、どれも確信がもてないし、納得もできるはずがないわ。それが聖世さまのノートに書かれていたことね。そんなことをしても、哀しみは癒えないし、未練は断てないし、何も変わらないわ。でも、そうでもしていなければ、自分を持て余してしまって、どうすることもできないのよ。それがわかるのは私なの。優貴ちゃんには無理かもしれない。もっとも、そんなことわからなくってもいいのよ。ただね、この機会に優貴ちゃんには言っておきたいの。あなたには、全然心配はしていませんが、こういう意識を持っていることって大事です。たくさんの男性から想われ、愛される女性を夢見てはいけないのよ。それを願望するような女ってちっとも素敵ではないのよ。想うことよりも愛されることが望みなの。人ではなくて想われていること自体が欲しいだけ。そんな品のない女にならないでね。
私は、よりによって、一番いけない人に聖世さまの秘密を明かしてしまったの。本当のことは何もいわなかったけど、聖世さまのことを知っていることにしたの。こんなことをすると嘘をつかざるを得なくなるのね。「聖世さまからあなたのことは聞いています」といってしまったの。彼女は驚いたし、私を疑ったかもしれないわ。でも、それまでお喋りしていたからでしょうね、だいたいのことは察しがついたみたい。経緯はわからなかったでしょうけれど。でも、そんなことはどうでもよかったの。私には隠しておかねばという抑えがなくなったし、彼女も遠慮しなくなったわ。ずいぶんと言い合いしたわ。こういうときって、教師と生徒という立場がよけいに感情的、攻撃的にお互いを仕向けてしまうみたい。不信感と嫌悪感を増幅させるのかしら。彼女には、別れた男が何を想っていたかなんてどうでもいいことなのね。心変わりしたのが自分の方であっても、謝るようなことではないといっていたわ。それはそうよね。謝られたりしたら聖世さまだって困られるでしょうね。でも、心変わりの理由はいわなかったわ。いえないのね。私はね、聖世さまの想い人が、あの哀しみと憤怒に満ちたノートの対象がこの程度の女かと思うと、聖世さまが、その想いがかわいそうになったわ。それは自分をかわいそうに思っていることなのね。なにを言い合いしたかなんて、はしたなくて優貴ちゃんにはいえないけど、その時から彼女とは話をしたことがないわ。彼女は、うちの高校から大学へと進学したけれど、私が彼女のクラスを担当することはなかったわ。まもなく、私は教職を辞めましたものね。でも、理事として、彼女のその後をみることができたのよ。彼女はどんどん大人になって、恋人ができて、聖世さまのことなんて思い出すこともなかったのかもしれないわね。私はね、聖世さまのことは調べてないけど、彼女のことは調べてあるの。というか、彼女の現在までを追跡調査してきたの。彼女に対してはどこまでも嫌な女になってしまったのね。優貴ちゃんがこれを読んでくれるころは、聖世さまのノートを見ているかもしれないけど、聖世さまは、彼女のことを忘れようなんてしてないわ。自分が忘れられてしまうことはわかっておられてもね。だって、彼女が心変わりしたのは、彼女が自分で決めたことだなんて信じておられなかったもの。こういう想いは吹っ切れないと私は知っていたの。優貴ちゃんは納得してくれないでしょうね。やっぱり、私しかわからないのかもしれないわ。優貴ちゃんも知っているように、私も親の反対で好きな方との仲を裂かれてしまったでしょう。私は、二度とほかのひとを好きになることはないと誓ったわ。ここが聖世さまと同じなの。本気でそんなことを言って、その誓いをまもろうとしていることが私には信じられたの。まもれなかったとしてもいいわ。ただ、本気だったこと、そうあるべきだと思っておられたこと、そこが嬉しかったの。私が自分の誓いをまもることができたのは、同じことを考えている人がおられると信じていられたおかげなの。おかげで、その後もお嫁にいかず、とうとう今日まできちゃった。優貴ちゃんはずっと否定的だったけど、人の生き方とか行動の決め手って大袈裟なものではないのよ。最後は個人と個人の問題。それも、知っているとか、親しいとか、行き来があるとかいうことは関係なくて、その思想、その感性に共鳴するかどうかだと思うの。信じてもよいと決めたことが、選ばれたり、検証されたり、確かめられたりした後の結果とは限らないのよ。ノートに書かれた聖世さまの誓いが破られている現実なんて知りたくなかったの。優貴ちゃんが聖世さまの現実を調べていたのは知っているわ。あなたの顔をみればおおよその結果はわかったわ。でも、裏切られたなんていうつもりはなくってよ。聖世さまが誓いをまもられることを求めていたわけではなかったもの。それに、お相手がその程度の女だったとわかってからはなおのことよ。だから、いつか聖世さまにはいってあげたかったの。どんなになったか教えてあげたかったわ。もちろん、聖世さまがお知りになりたいといわれたときだけって決めていたけど。でも、実際にはどうしたかしら。
もっと、もっと前に聖世さまは現れると思っていたわ。そのときは、もう新しい恋人ができたのですかって冷やかしてあげようと思ってたわ。お嫁さんをもらっておられたら、こんなもの見つからないうちに処分しなさいねといってあげるつもりでいたの。お若い時なら、彼女のことも知らないままにしておくつもりだったの。でも、いつまでたっても現れないので、もしかしたら、私のような生き方をされているのかなと思うこともあったわ。だから、後になればなるほど、お会いしたくなったし、おはなしもしてみたかったわ。でも、もう叶わないことになりそうです。優貴ちゃんは、あり得ないというでしょうけれど、聖世さまがもう一度あの山に登られるような気がいまだにするの。今になれば、とても懐かしくて大切な「思い出」ですもの、きっともう一度見てみたいと思われるに違いないと確信しているわ。大悲山の監視はこれからも続けてもらいます。地元の自治会に山の管理をお願いしていますから、決められた場所に何かあれば、私がいなくなってもこの家には連絡があるはずです。そしたら、きっと訪ねてこられるような気がします。そのとき、優貴ちゃんがどう対応するかは、お任せするわ。ただ、思い出はお返しして差し上げて。だって、元に戻さないで今日まで持ってきてしまったのですもの、お返しする責任はあるわ。そして、私のしたことをお詫びしてほしいの。あなたに、こんな人の秘密を押し付けるのは心苦しいけれど、封をしたままの聖世さまの思い出と彼女の調査報告書をあなたにお預けします。手紙に書いた聖世さまへのお約束にしたがうなら、大悲山の箱の中に戻さねばならないのですが、あなたなら、聖世さまもきっと許していただけるように思うの。いけないのは、始めから終わりまで私ですもの。 長い手紙になってしまってごめんなさい。 なん日かにわたって書いてきたけど、疲れてしまいました。この件については、優貴ちゃんとは議論になっちゃうので、あまりおはなしできませんでしたね。まだまだ、言い足りないのだけれど、すべては聖世さまがおいでになるかどうかですね。おいでになったときのことを思えば、優貴ちゃんが中身を知ってない方がいいと思うの。だって、聖世さまにしたら、自分お一人の胸に納めたものを女二人に知られてしまったなんて、きっと恥ずかしがられるに違いないわ。だから、見てしまっていたら仕方ないけど、未だなら見ないほうがいいと思うわ。 |
手紙はそこで切れていた。終わりなのか、まだ続きがあるのかわからなかった。この後には、何か別のことが書かれているような気がしてならなかった。
落ち着かない気分で聖世は辺りを見回した。優貴はまだ戻ってこない。座卓に手をついて、腰を浮かして優貴が座っていた辺りを覗き込むと、黒ずんだ大きめの封筒が置いたままであった。その中は、聖世の思い出のノートや手紙、写真であろうと察した。封が開けられたのかどうか、見ただけではわからなかった。それを持ってここから逃げ出したい衝動にかられたが、そんなことができるわけもない。しかし、何故にこれほど恥ずかしいのであろうか。なぜ、こんなにオタオタしているのであろうか。雪絵の手紙が聖世を嘲笑していたわけでもなかったのに。
それにしても、雪絵が、彼女・美希と接点があったとは驚きである。しかも、聖世とやりとりした手紙のことも、ノートのことも知ったうえで、自分のことで言い争ったという・・・。震えがきた。これは偶然なのか。いや、雪絵が京都に在住し、女子学園の理事、教員をしていたというのは事実である。だとすれば、雪絵が美希を知る可能性は、せいぜい数百人単位の範囲内のことになる。ならば、あっても不思議ではない。偶然だとしても可能性は低くはない。聖世は混乱して妙な確率の計算をしたりしていた。要するに、うろたえていた。
雪絵は美希に聖世のことは一切話してないというが、ほんとうだろうか。美希のその後は、現在は…。そういえば、美希の調査報告書というのはどこにあるのだろうか。
二 想い邂逅
礼儀正しく両手を添えて襖が引かれた。敷居の向こうで優貴が三つ指をついて頭を下げている。脇に置いた盆を持ち直して部屋に入ると、再び盆を置いて座り直して襖を閉めた。聖世は硬くなって座っているばかりである。碾茶椀と茶菓が盆に載っている。優貴が淹れてくれた一服の茶を飲み干して、聖世の緊張はやっと少し弛んだ。
「叔母の手紙はいかがでしたか」
何を答えろというのか。こんなにも長い間待たせていたことを詫びろというのか。自分が雪絵の期待どおりに生きなかったことを詫びろというのか。聖世は自虐的なことを思った。
「雪絵さんには申し訳ないことでした。もっと早くに気付いて、お会いしたかったです。きっと、だらしない私に失望されたと思いますが」
聖世は、いうべきことを最小の言葉で言っただけである。雪絵からこれだけの言葉をもらいながら、なんと紋切り型の感情のこもらない応え方をしているのだろう。情けない。
「私は、叔母さまのおいいつけどおり、埋められていた聖世さまのものは見ていないのですよ」
聖世が顔を上げると、優貴は白い歯を見せて、いたずらっぽく笑っていた。初めて見せる笑顔に救われて緊張が解けていくのがわかった。
「ありがとうございます。よかった。あんな恥ずかしいものを見られたら逃げ出したくなります」
聖世は言ったが、すこし落胆もしていた。妙なものである。雪絵が、かなり好意的にみていてくれたと思うと、この優貴にもなにかしらの評価をしてもらいたいと思っている自分がいた。しょせん「若気の至り」である。もう恥じらいなどとうの昔になくしたふてぶてしい老人でしかない。だいいち、聖世はほとんど内容を思い出せない。
優貴が「クスッ」と小さく笑った。聖世もつられて笑ったが、それは優貴が本当は聖世のものを見ていることのサインではないのか。そう思ったとたん、血が一気に顔に昇って、おかしいほど赤くなっていくのがわかっていながらどうすることもできない。汗が噴き出そうになる。
優貴は最初と違って優しい眼を聖世に向けていた。これほどの若さで上品に着物を着こなし、この屋敷に溶け込む清楚な麗人。この女の美しさは罪である。その前で、聖世は老いた醜い姿を曝していることをいやでも自覚してしまう。まるで鏡に写した自分を見せられているように鮮明にイメージできる。聖世が赤くなるのはその恥ずかしさのせいかもしれない。
そんなとき、襖が開いて、割烹着を着た堂々とした恰幅の女性が入ってきた。齢は聖世よりもかなり下ではあろうが、元気な「お母さん」といった風である。手にした盆には、ビールとグラス、それに小鉢が載っている。この屋敷のお手伝いさんと見受けられる。聖世が飲み干した茶碗を引くと、二人の前にグラスと小鉢を置いた。ビールは優貴の前に置く。
「まだ、お夕飯には早いですが、おくつろぎいただこうとおもって、ビールを用意させていただきました。先生はいけるクチなんでしょう」
口調がすっかり変わっている。聖世を「先生」と呼ぶが、もう、以前からの知り合いと話をするような親しみのある声で、顔はなにか嬉しそうに笑っている。そういえばこの部屋にあがってからかなりの時間が経っていた。庭に目をやると、夕暮れにはほど遠いが、陽が傾いて樹木の影が少し長くなったように感じる。驚くことばかりのうえに、優貴とのはなしにも、雪絵の手紙にも、緊張をしていたのは間違いない。そんな折に、優貴は聖世の疲れを察したかのようにビールを勧める。恐縮しながらも、聖世はビールを注いでもらう。ビール瓶を持ち直して優貴にも注ぐ。優貴は耀くような笑顔で、聖世は照れ笑いをしながらグラスを合わせた。ほどよく冷えたビールが喉に心地よかった。注がれるままに聖世は続けて飲み干した。聖世も少しだけ他人行儀な口調は改めたが、優貴のようにはなれなかった。
「先生は叔母さまの鏡でしたのよ。叔母さまは、先生の想いと決意に同調されておられたのですもの。いつかは戦友だとかおっしゃっていましたわ。叔母さまは、『人の心変わりというのは、変わる側と変わられる側の差があまりにもありすぎ』『変わられる側は哀しみよりもその理不尽さに耐えられないのよ』と話しておられました。だから、そのことをわかって、自分だけは変わらない生き方をするのだという先生に共鳴したんですって」
「確かに、そんなことをノートに書いていたように思います。その時は本当にそう思っていたのでしょう。情けないけど、ごらんのようにそんな生き方はしていません。雪絵さんにも、あなたにも、会わせる顔がないです。雪絵さんには、叱られるよりも、情けない気持ちが先にあって、ここに伺うのも躊躇してたんです。正直いうと、今日も覚悟がないまま来てしまったのです」
「叔母さまは、先生のことは知っていましてよ。でも、それを責めようとはされませんでした。そういう決心をされていたことが嬉しかったみたいです。そして、それを支えにして、ご自分は決めたとおりの生き方を貫かれました。叔母さまをそこまで強くする先生のノートに興味がありました。ゴメンなさい、本当は拝見してしまいました。でも、現在の先生を知っている私は同意しかねます。ですから、結果はご自分と逆の先生なのに、叔母さまがあんなにお会いすることを切望されていたのがちょっとわかりません」
聖世には返す言葉が見つからない。そのとおりだと思う。だが、だからこそ、それは消してしまいたい「秘密」ではないか。雪絵のように決意したままに生きたのなら、それは「勲章」として誇ってもいい。優貴が雪絵の手紙を見せるのは、それが雪絵の秘密ではなくて、むしろ誇りにできるからではないのか。
「先生は、美希さんがどうしておられるかご存知ですか」
!そうか、優貴は調査報告書を見ているのだ。だから彼女の名前を知っているのだ。美希の昔も現在も知っているのだ。しかし、そんなことを今さら問題にしても仕方ない。それを前提に対すればよい。
「いえ、まったく知りません」
「お知りになりたいですか」
「・・・美希はぼくのことなど忘れているでしょう。しかし、調査報告書なんてものは、その人のプライバシーそのものでしょう。われわれが見てもいいものなのでしょうか」
「聖世先生、興信所の調査なんて、その人の経歴程度のものなんですよ。誰と結婚して、いつ別れたとか、どこにお住いとか、先生でも私でも、その気になれば調べることができるくらいのものです。たいそうに書かれていますけれど」
そんな恐ろしげなことをいっているのに、優貴に微笑まれると聖世は頷いてしまう。ああ、この笑顔の前では何もかも許されてしまう。それほど彼女の顔は陰りがない。
「申し上げますと、叔母さまはね、美希さんの女学校時代のお友達からずっと情報をもらっていたのです。こちらの方がリアルで凄いでしょう。ほんとうに、叔母さまの執念には驚かされますわ」
なんと恐ろしいことを。美希は、結婚も離婚も親の家業の浮き沈みはおろか、どこに住い、何をしているかを追跡されていたばかりか、個人的な生活や人間関係まで雪絵に把握されていたという。一番気にしてもよいはずの自分が何も知らないままでいたというのに。それにしても、美希は離婚していたのか。それだけでも胸がザワザワする。いや、哀れとか可哀相とかいうのではなく、むしろ期待していたことが当たったような悦びさえある。なんとも複雑な気持ちになる。
「これは、先ほどお見せした叔母さまのお手紙と一緒にありました。でも、お手紙の続きではありません。叔母さまのメモ書きに近いものです。美希さんが、お友達に先生のことをどう話していたかまでわかりますのよ」
「そうですか・・・。あまりにもびっくりすることばかりが続くので、正直、混乱しています。それで、美希がぼくから離れていった理由はわかるのですか」
優貴が笑った。
「ふふっ。先生は今でもそのことが一番お知りになりたいのですね」
「今さらどうでもいいことです。が、それがわからないことが一番辛かったのは確かですね」
「美希さんがお友達にどこまで本当のことをはなされていたかわかりませんが、お二人は、美希さんのご家族に反対されたことがあったでしょう」
「反対はされました。しかし、それでも・・・」
「さらに強く結ばれていったとおっしゃりたいのでしょう。でも、彼女はそのことでお姉さんにきつく叱られたようです。彼女は、先生には言わなかったかもしれませんが、お母さんとお姉さんに説得されたようだと叔母さまは聞いておられます。先生の知らないところでそういうことがあったのでしょうね。さすがに、その内容まではわかりませんが、ともかく、それで彼女は先生と逢うのは一切断ち切ったようです」
「反対されたことは聞かなくてもわかっていましたよ。他に思い当たることは見当たらなかったから。しかし、それだけで終ってしまう仲だったとは今でも信じたくない気持ちに偽りはないです」
「先生が悪いわけでも、嫌いになったわけでもないことは美希さんもお友達にお喋りしていますのよ。でも、やっぱり熱が冷めたということではないのでしょうか。そこに、先生から何度もアプローチがくるのですもの、逃げるしかなかったのでしょうね。なんといっても、まだ高校生ですもの…」
確かにそうである。優貴にいわれるまでもなく、聖世はそんなことであろうと自分のなかではとうに総括している。しかし、そこに至るまでどれだけ美希の真意を疑ったか。心変わりを疑ったのではない、その逆である。冷めたのなら、なぜそういわないのか。嫌うなら、なぜそうだといわないのか。本当はそうでないのに、そう仕向けられているだけではないかと疑っていた。お目出度い話だが、それが当時の聖世であった。
「先生は、逃げる彼女を追っかけたでしょう。でも、お家に電話することもできず、お手紙も出せなかったのですね。そして、とうとう、彼女が学校に行くのを待ち伏せされたのでしたね。私は、先生のそのときのことを書かれたノートを拝見しました。夜も明けない真冬の冷たい路上で、人々の訝る目に曝されて何時間も待ち続けられたのでしたね。それなのに・・・」
「それ以上は言わないでください。それ以上は・・・。言葉では説明できない辛い思い出です。いくら昔のこととはいえ胸が疼きます」
「ごめんなさい。先生のノートを拝見しただけでもそれはわかります。会えないうえに、現在のように、携帯で連絡がとれるということもなかったですものね。何か誤解があっても、いきちがいがあっても、確かめる術さえなかったのですものね。やっとお逢いできる約束をしたのに、むごい仕打ちが待っていたのですね」
「なにもかもご存知でしたか・・・。そのとおりです。そして、結局、美希からは何も聞かないままでした。どんなことがあっても連絡だけはできるように工夫しておいたはずなのに何の連絡もない。郵便受けを日に何度覗いても手紙は着いていない。なにが彼女にあって、なにが彼女をそうさせているのか想像するしかないのです。いろんなことを想像してしまいます。見えない可能性を想像すると疑いが沸いてきます。それがどんどん膨らむのです」
「・・・ご自身しか本当にはわからない苦しみですね。差し出がましいことを申し上げてしまいました。お許しください」
「いえ、そんな・・・。もう、感覚、感慨が戻るようなことはありませんから、気分的には楽なものです」
聖世の正直な気持ちであった。もう、あの狂おしく切ない日々は苦痛を伴わない記憶でしかない。
「今だからお訊きできるのかもしれませんね。どうして逃げていく美希さんを最後の恋人だと定められたのですか。そんなに想われるお相手ではなかったように思ってしまうのですが。もっとも、結果からそう思うだけです。その点では先生も誓いを守られなかったのですから同罪ですよ」
「はは、同罪ですか。しかし、その時は理由がわからなかったというのがすべてですね。心変わりが彼女の本当の意思ではないと思ったからです。だから、ぼくだけは変わるまいと思ったのです。でも、だれにどう言われたにしても、彼女は自分の意思で決めたのはそのとおりでした」
「先生、それだけだったら、叔母さまは美希さんをそんなに嫌わなかったはずです。叔母さまは、美希さんが先生から贈られたカードやお手紙まで、お友達や新しい恋人に見せたりしているのが許せなかったのだと思います。それはしてはいけないことだと思います」
そんなことを美希はしていたのか。恋人が別れても交換した恋文は残ってしまう。愛が冷めた当人には戦利品になり、新しい恋人への手土産にされてしまうのか。なのに、それを取り戻すことは叶わないとは。
相手に読んでもらうためだけに書いたものが他人に読まれるなんて、思っただけでも恥ずかしい。そんなことを予感したら、だれが恋文など書こうか。だれが哀訴の文を残したりするものか。必死で想いをつづったのに、心の内を曝け出して書いたのに、後のない告白を書いたのに。
許さない!それで辻褄が合う、これで判った、いつか偶然に会った彼女の不可解な話とその時の含み笑いの意味が。ぞっとするほど憎々しくて傲慢な態度の意味も。他にもあるある思い当たることが。チクショー!自分だけが、自分だけが、知らなかったなんて・・・。
聖世も同じ罪を犯しているのだろうか。美希の恋文を大悲山に埋めたことがもとで雪絵と優貴に見られてしまった。しかし、美希がしたことと自分がしたことはまったく違う。自分はだれかに見せることなど思ってもいなかった。ゴミ箱に捨てられなかったから、焼いてしまえなかったから、遠くに埋めに行ったのである。美希の恋文などいまさらどうでもよい。恋の証文がなんになろう。それよりも、自分の告白こそ秘めておきたかった。
それにしても、いったい自分は何を掘り起こしてしまったのだろうか。想いの形見と名付けた思い出は、時を経て、なにを自分に語りかけようとしているのだろうか。もはや自分の手におえない、とんでもないバケモノに変質してしまっているのかもしれない。
優貴は聖世に注がれた何杯目かのビールにほんのりと顔を染めていた。空になった小さなグラスを、両手を添えて目の前に持ち上げて見詰めながら小首を傾げていう。少し甘えたように。
「先生は、今でも美希さんのこと好きですかー」
酔いが聖世を弛めている。聖世とは親子ほどの年齢差があるのだ。わだかまりを捨て、初対面であることも、他人の家中であることも意識しないようにすれば、優貴は娘と同じ年頃の女の子でしかない。
「そんな感情はもうないよ。復讐はいつかするつもりでいたけれど」
「復讐って、どんなことするんですか」
「さあ…。改まっていわれると困るけど。本気で考えてなかったのかな。いつの日か、彼女の前に怖い顔をして立つことは想像していたような…。復讐っていっても、べつに殺してやろうなんて思ってないですよ。ただ、このままでは終らせないという気持ちはあったね。これは、ぼくにそんなことをいう資格があるとかないとかの問題ではなくて、元々ずっと思っていたことです。ある意味では自分の支えのようなものでした。しかし、今は、いろんなことがわかってきて、本気で復讐を考えそうです」
「先生のおっしゃることは面白いですね。叔母さまがここにおられたら、どんなにお話がはずむでしょう。・・・普通、殿方は別れた女性にも『幸せになった噂を聞く方が嬉しい』とかおっしゃいません?」
「男に限らず、女だってそういう言い方をするじゃないですか。確かに、ふった相手がウジウジして病気になったとか、自殺したとか聞いたら嫌でしょう。そこまでいかなくても、ふった相手が不幸であるよりも幸せでいてくれる方が救われるというじゃないですか」
「先生は・・・、『ふられた方』だから『復讐』なんですか?」
「それもあるけど、そもそも『昔の恋人には幸せでいてほしい』なんて、嘘くさくって嫌いですね。『青春は美しい』というのと似ています。『夢と現実は違うから』なんて陳腐な理由ではないですよ。嘘ではなくて『うそ臭い』のです。若い優貴さんにはわかってもらえないでしょうが」
「『ゆき』と呼んでくださいな。ビールはもうなくなっちゃいましたから、お酒の冷たいのをご用意しましょうか。私もいただきたくなりましたから」
卓の上には、酢の物、焼き魚、蒸し物と酒の肴になるものが出されて、聖世は遠慮なく食していた。慣れたというより、居直ってしまったという方が当たっている。聖世には、ここは雲上人の住居、優貴はそこの姫にも観える。酒でも飲まねば貴高さに圧し潰されそうである。
料理はどれもあのお手伝いさんの手作りらしく、家庭的な味に聖世の酒はすすんだ。優貴は普段から手料理などしないようであった。そういう所帯染みたところがまったくない。冷酒を持ってきたお手伝いさんは『お嬢さん、あまりお酒をすごされるのは…。きょうは私もお屋敷にお泊りしますが、まだ明るいうちからお酒なんて、ほどほどにしてくださいね』と聖世の方を睨みながらいう。『けん制されているな』と聖世はわかっていたが、優貴が「大丈夫よ。私が呑むのではなくて、先生に呑ませて喋らせるんだから」と応えると、お手伝いの女性は首をふりふり、それでも笑顔で部屋を出て行った。
「それで、先生がそれを嘘クサイっておっしゃるのはどうしてですか?」
「うーん、そんな言い方って、自分が幸せでないとできないよね。自分が不幸をかこっているのに、ふられた相手が幸せと聞いて祝福する気になんかなりますか。できっこないですよ。別れた恋人に会ってもいいと思うのは、自分が相手より幸せになっている場合だけです。それって、なんか嫌味な見せつけになるでしょう。絶対に避けるべきです。敢えてするのは一種の復讐でしょうね」
「あー!そういうことなんですね。先生がお幸せになられて、美希さんがそうでもないということであれば、先生の復讐の準備は整うのですね。なるほどー」
さすがに「美希の不幸」とはいわなかったが、優貴は美希の不遇を知っているのだろう。だが、優貴が「復讐」などと品の悪い言葉を使うとは。話の内容のせいか、酒のせいか、優貴が聖世に気を許しているのは確かであった。この機に聖世は美希のことを聞き出してみようと思った。
「ぼくが幸せかといわれたらかなり疑問符が点きますが、美希は不幸なんですか」
「センセ…、優貴に悪い女になれとおっしゃるのですか。なって差し上げてもいいんですが・・・」
瞳が弛んで、いたずらっぽく笑っている。
「ぼくだって、本当は知らない方がいいように思います。美希が幸せか不幸せか、どちらにしても嬉しいと喜ぶことではないですから」
「慎重なんですねー。彼女に対するお心遣いなんでしょうか」
「いや、そんなことないです。これまでお聞きしただけで、ぼくだって悔しいです。彼女の不幸を望む小心な男ですよ」
「だったら、お役に立てるかも知れませんわ。でも、私に気遣いはしていただけないのですかー。優貴は、美希さんの履歴も、叔母さまが集めた私生活の遍歴も、噂も、彼女の現在のこともわかる書類を先生に見せることができますのよ。でも、それっていけないことですよね。美希さんにすれば嫌に決まってますわ。元々、そんな情報を集めるのがいけないことだったのですもの。雪絵叔母さまがそんなことされていたのはショックでした。でも、叔母さまは美希さんが許せなかったのと、先生にいずれ教えるためということで正当化されました。私も、叔母さまの意思を継いでいます。それに、先生の復讐のお役に立てるならという理由もあります。聖世先生、私に美希さんの調査報告書と雪絵メモをお求めですか?」
彼女は、美希の秘密を聖世に洩らす免罪符を得ようとしている。罪があるとすれば、求めた聖世が引き受けてくれるのかと問うているのである。元は、ただの幼稚な恋愛ごっこの破綻を大袈裟に嘆いた自分、それをノートに書き遺した自分、大悲山に埋めた自分、その存在を隠し切れなかった自分、そして消し去らなかった自分が悪いのである。知らない間に、知らない人を巻き込んで、聖世の初恋と失恋があぶり出されてくる。己が望んだわけではないのに、自分をふった女の不幸の噂まで伴って。
「そう聞けば、美希が幸せでないことはわかります。しかし、そんな彼女に会っただけでは、ぼくの心が晴れるとは思えません。それに、復讐するのなら、自分だけで、無慈悲に、残酷に、断固としてしなければ意味がないのです」
「先生はずるいです。私に美希さんのことをもっと言わそうとしてるでしょう。優貴には、小百合さんが幸せか不幸せかなんて判断できませんわ。でも、美希さんが幸せならどうしますか?それも、とってもお幸せとわかったら」
「優貴さんも結構ずるい訊きかたをしてるじゃない」
「『優貴』と呼び捨てにしてくださいな。私は久しくそういう呼び方をされてなかったですから、その方が嬉しいです」
聖世は照れたが、優貴のいうとおりにした。ただ、やっぱり口調はぎこちないままであった。
「ぼくはね、美希が幸せだったとしたら、やっぱり先ほどいったように面白くないに決まってる。やっぱり彼女には不幸せでいてもらわないと駄目なんです。幸せな彼女を見せつけられるなんて、とうてい耐えられない。ぼくをふったのに幸せになったら、ぼくでなかったからよかったことになるじゃないですか。やっぱり、ぼくをふったのを後悔させたいという思いはあります。でも、それが自分の幸せを見せつけることだなんてぬるいことをいう気は毛頭ないけど」
「先生は正直ですね!それを聞いたら、叔母さまもきっと納得されたと思いますわ。復讐はご自分の手で…男らしいです。もう、美希さんの報告書も雪絵メモもご覧になる必要はないですね」
聖世は何かいおうとしたが、優貴が遮って話題を変えた。
「先生、陽が傾いてきました。お庭に出て少し歩きません。夕陽がきれいだと思いますよ」
聖世が庭に目をやると、確かに夕暮れの残照に庭全体が赤く染まっていた。いわれるまでもなく、みごとな夕焼けが想像できた。だが、思った以上に酔ってしまった聖世の高揚した気分は容易に治まらなかった。グズグズと座り続けている聖世の両手を優貴が握った。聖世はあわてて腕を引こうとしたが、優貴に引き上げられるようにして立たされた。優貴は嬉しそうに笑っているが、聖世は赤くなるばかりであった。
まばらに樹があって小さな花が咲いているだけだが、開放感のある広い庭に下りた。二人で夕陽を見ながら歩いては立ち止まる。聖世は彼女を「ゆき」と呼び、たわいのないことを話して笑いあった。優貴がこの大きな屋敷と雪絵の遺した資産を一人で相続することになったが、その手続きを聖世に依頼するという。雪絵の養女となりその資産を継いだのだから、優貴はそれをまもっていかねばならないが、若い彼女にはいいしれない重圧があるのだろう。聖世に後見人的なものになってもらうことで解放されたのか、晴々としている。
後ろ手に両手を結んで、優貴はルンルンという感じで聖世の少し前を歩いている。長い髪を結わえた手作りの花輪のようなリボンが可愛い。下駄なのに弾むような歩き方をしている。何がそんなに楽しいのかと後ろをついていく聖世に、優貴がひょいと振り返った。
「先生の若い時って痩せてたんですねー」と一枚の写真を手にかざして聖世の顔の前に突き出した。モノクロの古いスナップ写真だが、聖世はすぐにそれがわかった。美希とのツーショットの数少ない一枚。美希も自分もお気に入りだった一枚。彼女のことを思い出すときは必ず想い浮かぶ写真であった。もう一度見てみたいものを選べといわれたら、間違いなくこの写真を挙げたであろう。
「美希さん、かわいいですねー。先生も素敵です」
「嫌だなー、そんなものまで見られてたとは。恥ずかしいから返して!」
聖世は一番見たかった写真の出現にドギマギしていた。早く手にとって見たい。同時に胸が痛くなった。
「もちろん!先生のですもの。でも、裏に書いてある言葉にも感激しました。憶えていらっしゃいますか?
「え、何か書いていた?」
聖世にはまったく記憶がない。写真の裏?感激?
優貴は嬉しそうに腕を上の方にいっぱいに延ばしてかざし持った写真の裏を見る。また、昔の力んだ何かが書いてあるのだろう。それを優貴に冷やかされるのがこそばゆい。
「読みますよー」
美希の声は弾んでいた。
拒絶を恐れて告白はない。
その恐れを越えたからといって勇気を讃える必要はない。
拒絶の後に息をしているのだって。バカな。立ち直れる程度の告白など、たかが知れているではないか。
立ち直ることなどおぼつかないまで思い詰めよ。
拒絶の後に残された人生などないと。
それが告白なのだ。
「よくわからないけど、すっごいなーって思います。これって、安易に告白なんてしてはいけませんっていうことですね」
「急にいわれても・・・。よく見ないと思い出せないから」
「はいっ。解説してくださいな」
聖世は写真を受け取っても、しばらくは裏よりも写真そのものに目が釘付けになった。あの短い幸せな時代の一瞬。あぁ、こんな顔をしていたのか。眩しそうにしている自分の隣に思いっきり笑顔の美希がいる。自分自身は、今では自分であることを疑うほど落差がある。美希も同じように変わってるのだろうか。そう思うと複雑な心境になって裏返した。自分の字体を見て、ようやくそれを書いたときのことを思い出してきた。やっぱり、目いっぱい力んでいる。聖世は苦笑するしかなかった。それを見ていた優貴が話しかけた。
「『勇気を讃える必要はない』ってどういうことですか?」
「告白って、拒絶された場合を想像すると怖くてなかなかできないでしょう。その怖さを克服して告白するのはいちおう勇気があるってことになるよね。でも、ぼくが言いたいのは、ふられる覚悟をしただけでは誉めるほどのことはないということ。『拒絶』というのはふられちゃうということだね。拒絶されたら、もう立ち直れなくなるほどの告白だけが本当の告白だといってるわけ。つまり、告白は生涯に一度切りということ。
「ワー、すごい、すごい」
「優貴はそんな告白をされたい?」
「うーん。そこまで思い詰めてくれての告白なら嬉しいです。でも、そんなことわかってたら嫌だな。断れなくなりそうですもの」
「負担になるわけか。でも、やっぱり嫌なら断るでしょう。相手が立ち直れないからといって優しくするのはかえって罪深いことになりませんか」
「なるほどー。で、先生は一度切りの告白をしちゃったのですね。 あ、赤くなってるー」
「冷やかしては駄目。そのとおりなんだから」
「ふーん。それで二度目はないのですか」
「・・・たぶんなかったでしょう。ただ、それは拒絶が怖いからできなかったという方が正しいかな。断られるのが怖いただの弱虫男ですよ」
「そんなの、してみないとわからないでしょう」
「女性は本心って見せないでしょう。優しくしてくれるから勘違いして告白したとたん、嗤われたらどうするのですか。それこそ恥ずかしくて生きてられないかもしれない。でも、どちらにしても、もう、ぼくには関係ないです。もう、告白することなんてないもの」
「ふふ。そうかしら」
優貴は聖世の手から写真をとって、もう一度聖世を見詰めた。
突然、
「せんせい!どうしてこんなに変わっちゃったのですか。お腹がこんなに出てしまってー! 」
優貴は聖世のお腹をポンポンと叩く。聖世が逃げるふりをすると、優貴がキャッキャッと追いかける。
脈絡なく聖世は思い出した。 訊いていたのは美希の現在だった。
「優貴は現在の美希を見たことがあるの?」
「ありますよー。写真だって撮ってありますよー。お仕事しているところですけどねー」
聖世の出腹を叩きながら優貴はそんなことをいった。美希は働いているのか。どんなことをしているのだろう。
優貴は手を止めて、聖世を見た。少しふくれている。
「先生が現在の美希さんに会うとすると、嫌がられるでしょうね。きっと見られたくはないでしょうね」
宙を見詰める優貴は、持っているはずの興信所の写真などを思い出しているのかもしれない。
突然、真顔でいう。
「先生をふったからでしょうか、あの方はご夫婦運に恵まれなかったようですね。二度のご結婚は二度とも悲惨な結果だったようです。少なくとも、先生とお別れしてよかったという結果にはなっていません。先生と続いていたらどうなったでしょうね・・・。」
「そうですか…。美希も苦労しているのか。別れてから遇ったといっても、彼女が学生のころだったからね。ぼくには、かつてのことなどこだわらず、自分のように新しい恋人を見つけたらいいといってたけど」
「美希さんだって後ろめたい思いがあったのでしょうね。私は許せるけど、雪絵叔母さまは許せなかったみたい。でも、確かに、それって言われる方は嫌でしょうね。先生は悔しくなかったのですか」
「そりゃ悔しかったです。でも、バカですね、『それでもぼくは変わらない』と言い張ってました。そして彼女にも同じことを求めたのです。本当にあきれられ、バカにされたと思います」
「お約束だったのですから、先生のおっしゃること、なされようとしたことは筋が通っています。でも、新しい恋人ができたお相手におっしゃっても無駄にきまってます」
「本当に馬鹿ですね。でも、ぼくだって言ったことを貫けなかったのですから、彼女を責める資格なんてないです」
「お相手が誓いを破られたのですから、先生がそんなこと思われることなんてないのに。でも、美希さんが恋多き女性であったことは確かです。先生と添い遂げるなんて無理だったんじゃないでしょうか」
「『約束はまもらねばならない』これは条理です。恋人どうしだといって、男と女の関係だといって、この条理が当てはまらないとはいわせない・・・。それが当時のぼくのこだわりだったのです」
「先生って、ほんとーにお馬鹿さん!おひとよし美希さんは、いっぱい、いっぱい楽しんでたのに、先生はそんなことにこだわって」
「しかし、今は苦労してるんでしょう」
「罰が当たったと思えばいいじゃないですの」
「いや、ぼくだって、そんな偉そうなこといえる生き方はしてこなかったのだから」
「あれ?復讐はされないのですか。先生が美希さんに会うだけでも相当なものですよ」
「そんな、彼女が弱ってるときに、それを見に行くようなことはしたくないです」
聖世は、優貴の前では本音をいってなかった。格好つけているが、今の自分だって充分醜いではないか。見られたくないのは自分も同じなのだ。
「先生!せんせいは何十年も封印してこられた思い出をようやく取り出しに行かれて、そしてここに来られたのです。叔母さまも私も、ずっとお待ちしていたのです。もう、その封印は解かれていたのです。これは、なんといっても叔母さまがいけないのです。そして優貴も叔母さまの罪を引き継いでいます。そして、美希さんの秘密まで収集してしまいました。先生にこれをお渡ししなければ、私には意味のないものです。先生がお望みなら差し上げます。それでなければ、やっとここに来ていただいた意味がないですもの」
聖世は困惑していた。美希合のことを知りたいという思いがなくはない。しかし、それはしてはならないような気がした。ほんとうに、彼女以外の女を想うことなく今日に至ったのならともかく、軽薄で自堕落で、何度も恋をして喪った普通以下の男ではないか。ここで、美希の秘密まで、他人が持っていたことを奇禍として覗き込むようなことをすれば、もう最低の男になってしまう。それに、美希が幸せでないことはわかった。四〇年前に自分を捨てた女は幸せになれなかった。それだけで胸のつかえは取れた。
「申し訳ないですが、やはり、美希の報告書も雪絵さんのメモも見ないことにします。彼女に知れることがないとしても、ぼくに見られることは嫌に違いないです。焼き捨ててください。そして、ぼくのノート類も」
優貴は黙って聖世を見詰めていたが、かなりの間をおいて「わかりました」というと、何もかも忘れたような笑顔に戻った。
「でも、先生の思い出は未だお返しできませんことよ。だって、とっても面白いのですもの。優貴が先生の秘密の思い出を持っていることをお忘れないように」
優貴は、それで話は打ち切りというように、向きを変えると聖世を後ろにして歩き出した。
西山に沈みかかる大きな太陽に射られて、優貴と聖世の影が庭に長く伸びている。前を歩いていた優貴がふりかえると、逆光に優貴の顔も姿も黒いシルエットになっていた。明るい陽に晒される思い出も、見る人、見る位置でその正体が見えなくなる。ならば、この優貴が自分を見る位置は、聖世を明るい光のなかで見ていると思いたい。そういう人の手にあるなら恐れることはない。いずれ聖世の想いの形見はすべて返されると信じることができる。優貴は、自分の誓いをまもらなかった聖世を少しばかり責めたいだけなのである。それが雪絵に対する侘びなのかもしれない。
シルエットになった優貴が何かを手にしているのがわかったが、背後の太陽が眩しくて見えない。近づくと一枚のノートの切れ端を聖世に向けて差し出している。変色してシミだらけのそれを間近で見るまで、聖世はそれが何であるかわからなかった。
「先生、優貴はこれが大好き。破いて持ってきちゃいました。その時も、こんな春のお陽さまがつくる影だったのですかー?」
秘めていた詩をヒラヒラさせて、優貴はハシャイでいる。だれにも見せないつもりで創った詩だから、下手を恥じなくてもよいのに聖世は赤くなった。
なお暮れそびれしは春の宵
いまだ沈まぬ大輪に
雲は早くも朱をおびて
地に在るものは影を持つ
長く伸びたる君が影
離れて立ちし吾にても
手をさしかざせば吾の手は
君が肩さえ届きたる
おもわず引きし己が手は
君に触れたる悦びと
高鳴る胸のときめきに
さとられまいと
握りたる
黙して路を進むれば
長く射したる陽光に
さらに伸びたる君の影
重なりしは吾の影
ふと見上げれば君が顔
笑みもて吾を見つめおり
秘めたる想いを知りたるや
いかに想いを隠さんと
意味なき言葉も恥ずかしき
いかに伸びたる影なれど
今は離れし君が影
ただ立ち尽くす吾を見て
傾けたるは君が顔
少女の笑みも隠さでや
にわかに瞳を輝かせ
鏡の前に立つがごと
影を見つつの舞いしぐさ
地に映されし横顔は
睫の様さえ現われぬ
吾はかなたを見つめしに
君は吾を見つめおり
ふたたび影に目をやりて
うれしきさまにて
身を折りぬ
吾は知りたる君が意を
身を引くいとまもあらばこそ
地に映したる君が影
われに口づけせんものと
ついには吾と重なりぬ
まだ沈みきらない大きな太陽が周りの雲を朱に染めていた。火照った顔に吹く夕暮れの風が心地よい。四〇年ぶりに拾い出した想いの骸は思いもよらない方向へ聖世を誘った。遠くに埋めたはずの過去はそこになく、こんなにも近くで自分を待ち続けていたとは。なにもかもが驚き、すべてが想像を越えていた。
睡眠中の夢であることを自覚しながら夢を見ることがある。何度もこれは夢だと思っているのに覚めない不思議な夢を聖世は見ることがある。今もそんな夢を見ているのだろうかと不安なので、覚めていることを確認してみる。陽の温もりに実感がある。訝りながらも笑っている優貴と目が合えば心臓がドキドキと音をたてる。それでも安心できないでセブンスターをくわえて火を点けた。無作法は承知であったが、優貴は驚いたような顔をしただけで「灰皿をお持ちしますね」と縁の方に駆けて行った。吐き出す煙が流れる様を見つつ煙の味を確かめて、聖世は「夢ではない」と結論した。確かめるためにしているそれぞれの所作が幸せの確認であった。
優貴が聖世からいろんなことを聞きたがっているのはわかっている。聖世が赤面しながら洩らす思い出も優貴にとっては楽しくて仕方がないものらしい。聖世にも聞かせたい少年のような秘め事がないわけではない。優貴にも秘め事があるように。話してもよいと思える相手、聞いてくれる相手がいるのは幸せである。優貴にはもはや秘密を知られることにはならない。封栓を開けられて見られてしまえば隠す理由がない。翳のある秘密ならこうはいかないが、思い出程度の秘め事なら恥ずかしいだけで濾過すれば無害になる。もっとも、雪絵と優貴の使い方次第では毒にもなりかねなかったのだが。毒を含んだ秘め事はまだまだある。形のあるものは消せるとしても、内にあるものを閉じ込めておく自信はない。心の封栓が溶け出したときはどうすればよいのか。それが次の課題であるが、心地よいこの酔いに委ねて今は何も考えまい。
少し離れて、優貴が自分の影を見ながら着物の袖を揺らして舞っている。地に映された優貴の影も大きく袖が躍動する。長く伸びた自分の影があやうく優貴のそれと重なりそうになるのを見て、聖世は身を引いた。